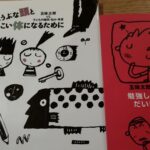「学校に行かない学び方」
今回の番組内容はとてもよかったです。
自分のやりたいこと学びたいことは自分で決める。
必要を感じたら自分で学び始める。
それは、学校の教科の勉強である必要はない。
「知りたい」「できるようになりたい」という思いは誰も持っている。
子どもを学校に適応させるのではなく、環境を子どもに合わせる。自分に合った学びの場が大事。
「学校しかない」と思ったら追い込まれてしまう。何が辛いかというと、「学校の行っていない自分を引けめに感じること」学校だけではなく、いろんな場があると安心できる。
「学校に行かなくてはいけない」「学校に行かせたい」というのは親の勝手な思い。どこに行くか何をするかは子ども自身が決めたらいい。
勉強とは「学校の教科」の勉強だけでなく、本人が 「知りたい」「できるようになりたい」という思いから始まる。だから必ずしも学校に行かなくてもいい。
大切なことは本人が生き生きしていること、楽しく学ぶこと。
2月3日に再放送がありますよ。
ウワサの保護者会「シリーズ不登校 学校に行かない学び方」
ウワサの保護者会「シリーズ不登校 学校に行かない学び方」
投稿日:
執筆者:azbooks