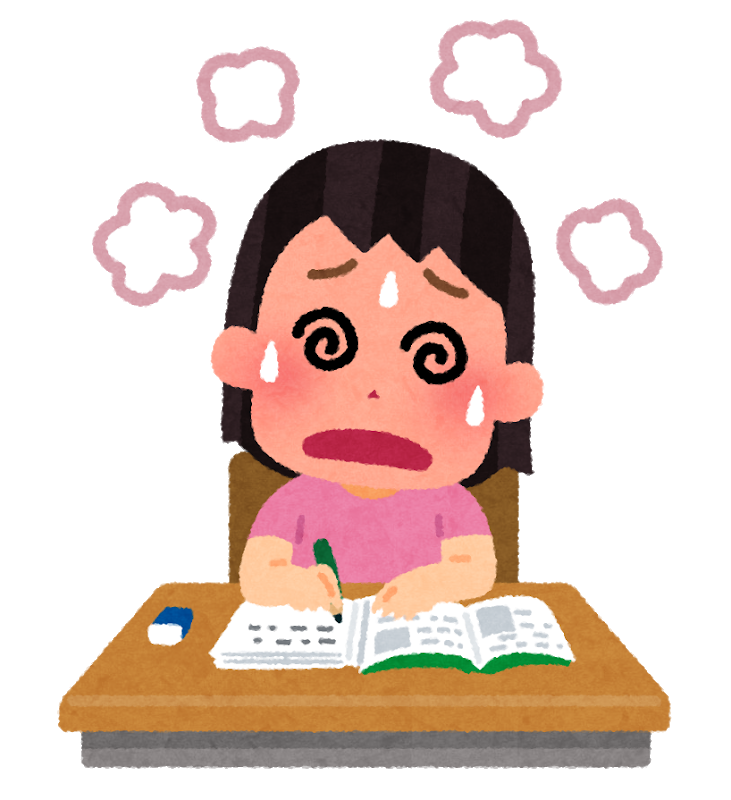
コロナの影響で学校が休校になり、教育関係者は「学びを止めない」と必死になっています。オンライン授業競争がまずます激化しています。
学校からyoutube配信「休校中も学べる」ネット無料教材が続々登場
そもそも、ここでいっている「学び」とは何を指しているのでしょうか?どんなことを意味して使っているでしょうか?
私はそれは「学校でやっている教科書の勉強」のことを指しているのだと考えています。
今、文科省や教育関係者、親も含めた多くの人たち「学びとは教科書の勉強」のことだと考えていますが、学びとはそんな狭い範囲のものではありません。国語や算数のテストでいい点数をとることではありません。
基礎学力とは何か?学校の勉強ができることではありません
「生きる力」とは言われたことに従い、与えられたことをこなすことでは絶対に身につきません。
新学習指導要領の柱「考える力を育てる」ために最も必要なこと
子どもたちは学校に、社会に何を求めているでしょうか。
はたして子どもたちは「学びを止めないでほしい」と思っているのでしょうか?
「学校に行って勉強したい」と考えているかというと、そうではないと思います。
そもそも「勉強ってつまんないよね。だからやるのはたいぎい」っていうのがほとんどの子どもの意識じゃないかと思います。子どものニーズがないのに勉強させることは、欲しくもないものを「押し売り」されるのと同じだと思います。
授業日数とか教科書やドリルを終わらせようとしているのは、教育関係者であって子どもはまったく必要感を感じていないと思います。あるとしたら、多くの子どもは受験のために、次の学校の入学試験に合格するためにしかたなくやるしかないという意識だけだと思います。その目的は次の学校に進むためであって、学びを楽しむことではありません。
「勉強が遅れる」という親の不安はあるかもしれませんが、子どもはそれを求めているんでしょうか?
これまで学校で子どもたちが学ぶ意味や学ぶ楽しさを感じているのなら、大人が「学びを止め」なくても勝手に学びます。自由に個々の子どもが学びたいことを続けていきます。
コロナ対策による臨時休校で学校が今できうる子どもたちへの対応策
子どもは学校に「勉強以外のもの」を求めている

子どもたちが求めていることは、友達と会いたい、好きな人に会いたい、おしゃべりしたい、遊びたい、思いっきり動きたい、おしゃべりしながら給食食べたいなどであって、「学校に勉強をしに行きたい」と思っている子はごくごく少数です。学校に「勉強以外のもの」を求めているのではないでしょうか。学校が再開した時にやりたいことは教科書の勉強ではなく、友達に会いたいということです。
休校中のの宿題、子どもがどっさり持って帰ってますよね。
見るだけでやる気は失せてしまう。
宿題をしなくて困っているのは子どもではなく親です。子どもは何にも困っていないと思います。
子どもが「やりたい」と思えるような宿題の出し方ができなかったのは、学校の責任です。子どもには責任はありません。親にもさせる義務はありません。
なんのために宿題出しているのか?
そもそもの学校の本来の目的って何なのか?
それを考えないで、ただただ義務的に学校で勉強させたり宿題を出しても子どもはやる気にはなりません。
やる気にならないから強制すればするほどやるのがイヤになります。勉強がどんどん嫌いになっていきます。
子どもは学校に何を求めているのか?
まずそこから考え直して、子どものニーズに応えることから始めた方がいいです。少なくとも子どもたちは学校に行って勉強することを求めていないと思います。勉強するのは二の次でいいです。
宿題がダメなのではなく、宿題の内容と出し方に問題がある
子どもはなぜ宿題をさせられるのか
宿題は、出す側の自己満足ですから、宿題が出たとしても、やりたいことだけしたらいいです。やりたくなければしなくていいです。
休校中の宿題、公立校では約半数がイヤイヤやっている
宿題の功罪について詳しいことはこちらを読んでください。
子どもに夏休みの宿題をやらせなくていい理由
「夏休みの宿題の意味」って何ですか?宿題代行業者が成り立つ背景とは
課題とはいえない夏休みの宿題なんかしなくてもいい、思いっきり遊べ!
子どもが宿題をしない、どうしたらするようになるでしょうか?
なんとかして子どもに宿題をやらせたい!親御さんへ、子どもにやる気を起こさせる方法
【小学生の保護者対象】休校中の学びに関するアンケート結果
【休校中の学びに関するアンケート概要】
実施期間:4月27日(月)〜4月30日(木)まで
調査方法:インターネットでのアンケート調査(SNSにて広報)
対象 :休校中の小学生のお子さんを持つ保護者の方
総回答数:438件
「友達や先生に会いたい。つながりが欲しい」
・オンライン授業の実施率はわずか14%、双方向は全体の2%のみ。
・学校再開に向けて、授業スタイルの変化によって子どもが自学できる力を養う
・何でもかんでもオンラインとなることに子どもが違和感を感じる、窮屈さを感じている。
(引用元:放課後NPOアフタースクール)
【緊急アンケート結果公開】休校中の子どもたちが最も求めていること









