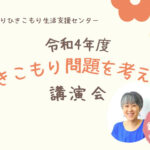「避難所で我慢を強いられるくらいなら自宅にいた方がいい」
災害で避難所生活を送ることを不安に思って自宅に留まる人が少なくないようです。
もし自分が体育館に避難したら一日ももたないと思う。
自分が体験した鳥取県中部地震でも避難所に行くのを躊躇い自宅で不安な夜を過ごしました。
もし避難所が安心して暮らせる環境であればほとんどの人が躊躇なく避難所に行くと思う。
「避難場所」として体育館や公民館などは指定してあるが、そこでの「暮らし」は想定されていない。あくまでも「一時的な避難」だが、実際には長期滞在を余儀なくされる場合が多い。
水も飲めない、顔も洗えない、トイレが使えない、風呂はない。慌てて扇風機やクーラーを調達しているが、猛暑で何人もの人たちがぎゅうぎゅう詰めの状態で、避難場所で過ごすことで心身ともに健康状態は悪化していく。
さらに社会的な障壁のある人にとっては命にも関わる。
だから「避難しないで自宅で過ごす」という選択をする。
このたびの大水害でも「安心できる避難場所」が設置されていたら自宅にいて流されて亡くなる人はもっと減らせたに違いない。
だから、これは自然災害というよりも「人災」といってもいい。
「避難場所なんだからしかたがない?」
「みんなが必死で耐えているんだからそうするしかない?」
もしかして、多くの人はこう考えて諦めているのでしょうか。
はたしてそうでしょうか。
災害支援はボランティアで支えられているという現実もある。
とても個人や地域の努力では解決不可能だ。
快適な避難所生活までは要求はしない。
しかし、災害対策予算としてもっともっと避難場所での「暮らし」のための予算を計上すること、それが災害大国ニッポンの政策として重要なことだと思う。
命を守るためにもっともっと国のお金が必要だ。お金の配分を見直す必要がある。
自然災害を防ぐことはできませんが、安心して過ごせる避難場所の設置、身近な情報発信などで二次被害は防ぐことができます。
これだけ自然災害が多いにも拘らず、今の日本はその備えができていないため「公的な人災」による被害者が多く出ます。
だから、「震災関連死」という犠牲者が多く出ていますが、これは自然災害というよりも「人災」といってもいい。
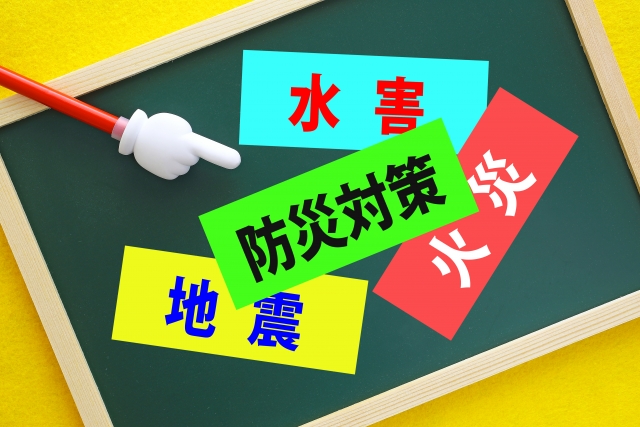
「みんなが我慢しているんだから・・・」
「みんなが辛い思いをしているんだから・・・」
これで終わらせてはいけません。
避難勧告や避難指示は出されているのになぜ非難しなかったのか?という無責任な専門家や評論家の意見も多いです。
しかし、避難できない、避難所に行かない理由があります。
その理由をきちんと把握して避難しやすい体制を整えていく必要がありますね。
災害に対する備え、「想定内」でまだまだできることはたくさんあります。
災害の教訓を生かすとは、二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な行動である。
鳥取中部地震もっとローカルな情報が欲しい、個人メディアの方がタイムリーな情報がキャッチできるにも書きましたが、テレビをはじめとするマスメディアの災害報道もっとローカルな情報が欲しい 個人メディアの方がタイムリーな情報って必要な人に必要な内容だと思えない。
必死に家族を探している方にインタビューとか、ありえない。
なんのための誰のための報道なんだか?
メディア向けのパフォーマンスだけの視察なんか必要ありません。
そんな人が来るだけ迷惑です。
鳥取県中部地震は報道などで伝えられていることと倉吉の実際の状況は違う
鳥取中部地震で現地にいたときも、こんな報道は全く役に立たないと感じました。
外部に流すニュースなどでは地震の様子やメカニズムなどを解説していますが、現場ではそんな情報はなんの役にも立たないのです。もっと細かい情報を早く知りたいのが現地のニーズなんです。
メディア関係者はそれに気づいていないのでしょうか?
FBなどで現地から個人で発信している情報の方が役に立ちます。
とてもありがたいです。
それよりも実効性のある具体的な施策を作って実行することです。
自然災害大国の避難が「体育館生活」であることへの大きな違和感
地震・災害・水害にあったら、どうすればいい?
毎度出てくる「想定外」という言い訳。
備えはできる。
「人災という被害」を防ぐこともできる。
そのために教育があります。教訓に学ぶこともできます。
最も大切なことは「自分事」として考えることです。
そのために必要なことは何か考え実行することです。
「水害にあったら、どうすればいい?」 このチラシが、とてもわかりやすい
“体育館で雑魚寝”は異常 最低限の安全を守る国際基準「スフィア基準」
「体育館を避難所にする先進国なんて存在しない」災害大国・日本の被災者ケアが劣悪である根本原因
日本での「美談」は、欧米なら「人権侵害」「ハラスメント」になる。
コロナ対策、災害への支援もあとは自分たちで頑張れ?

この度のコロナ対策、災害への支援などを見ていて、結局は自分の命は自分で守るしかないのだと考えるようになりました。
政府や行政は口先だけはいいことを言っていますが、実態が伴っていません。具体的な支援がまるで届いていないのです。
「いうことはいったから、あとは自分たちで頑張れ」なのです。
「自分事」ではないのです。
だから、多くの人は声を出すこと、行動に移すことを諦めてしまう。何の期待も持たなくなる。
「コロナだから仕方がない」
「自然災害だからどうしようもない」
私はそうは思いません。救える命は救えます。
「困ったら相談を」と言いますが、本当に困っている渦中の人はそれができない。形だけの窓口はあっても、そこへ行くまでの壁が本当に高いのです。
声を出せるまでには時間も必要なのです。そこへの距離は物理的にも精神的にも本当に遠いです。
守れる命が守れなくなっているのが、今の日本の姿だと思います。
そのような根本的、根源的な問題を見つめなおす必要がありますね。
その一方で、地域で周囲の人たちのために無報酬でがんばっている人たちがいます。
目の前の困っている人をなんとか助けたいと懸命にがんばっている人たちがいます。
本当にありがたいです。