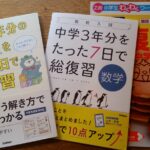そもそも「不登校」か「不登校じゃない」と分けることがナンセンスなんです。学校もあり学校以外もありなんです。
だから、私たち大人が手を取り合って子どもたちがのびのびと学べる場所がいろいろできればいい。
今、鳥取県では高校生や大学生も不登校の子どものために何かしたいという思いで行動を始めています。
それがうれしいです。
いろんな子がいていろんな人がいる。
それなのにみんなが一律に同じ時間に同じ空間で同じことをすることに無理があります。
だから学校が合わない子がいるのは当たり前です。
多様性を認めるとは観念ではなく具体的な場作りなんです。
子どもも無理している
保護者も無理している
教員も無理している
みんなが無理な要求に無理して応えようとしているんじゃないの。
だったら、何をどうしたらいいのか?
無理しないで通える学校を創るしかないよなあ。
どんな学校だったらいいかって?
みんなが無理しないで行ける場所であること
自分のやりたいことが自由にできること
自分で課題を見つけそれを追及する学習
児童生徒そして教員の自由が保障される学校
子どものことを100%信じられる職員集団で構成された学校
個に応じた支援が「本当に」できる学校
「その子が学びたい場所が学校」
まったくその通りだと思います。
こう考えると「不登校」という概念は意味をもたなくなります。
「不登校」というのは「学校に行くのが当たり前」だということが前提になっていますが、「学び」を中心に置くと「学校に行く行かない」はどうでもよくなります。
学校に行くことで評価されるのではなく、その子の学びで評価する。しかも他者評価ではなく自己評価であることが重要です。
学校ありきではなく学びありきです。
学校で宿題、担任、定期テストをやめることはすぐにでもできることです。
今の学校は学習指導要領で定められていないことまでやっています。
その理由は、「他の学校はやっているのにうちだけやめるわけにはいかない」からです。
教員の長時間勤務は時間を切ればいいというものではありません。仕事量そのものを減らさない限り教員の仕事は無限に続きます。
全国一斉学力調査もする必要はありません。
運動会や音楽会、学習発表会などの行事のための練習も卒業式などの儀式の練習もする必要はありません。この他にもしなくていいことはたくさんあります。
学習指導要領に定められたことだけやればいいです。
自分の意に合わない不自由で閉鎖的な空間に閉じ込められてただじっと我慢しなければならない。
これでストレスを感じない方が変だと思います。
「そんな所に入るのは無理だわ。」
そう思う子どもたちがいるのは当然です。
これはもはや「学校」と呼ばない方がいいかもしれません。
苫野さんの創る新しい「学校」に期待しています。
学年とクラスをなくせば不登校は激減する
問題は子ども本人に障害はないのに「障害児」にさせられていること
「発達障害」という概念は精神科医が勝手に作り上げたものです。それを「障害」という名前をつけたために多くの間違いと偏見を生んでいます。「害」をわざわざ「がい」とひらがなに書き換えて表記するなどおかしなことをしています。本質はそこではありません。
子どもが「人と違う」「みんなに合わせられない」「学校になじめない」から「発達障害」なのではありません。そんな診断は間違いです!
人にはみんな違いがあります。それは個々の持っている「特性」であり「障害を持っている」のではありません。
障害は私たちの側にある偏見や環境など社会的な障壁です。
しかし最近では「この子は学校生活で他の子に合わせられない」「集団行動ができない」という理由で診断をすすめるケースが増えています。これを「発達障害ブーム」といいます。
それは「特性のある子ども」(発達障害ではなく)が増えてきたのではなく、学校側や社会の側にある障壁が増えたこと、診断をする件数が増えたことによって「発達障害と診断された件数」が増えてきただけです。「特性のある子ども」が増えたのではなく、そのような判定が増えてきただけです。ここを間違えてはいけません。
そして最も重要な問題は、親も教員も含めた世間の間違った理解と社会的な障壁による「二次障害」です。これは「特性」によるものではなく、他者によって人為的に作られた障害です。特性を理解するには、まずは正しく学習することが必要ですにも書いていますが、子ども本人に障害はないのに「障害児」にさせられ、偏見の目で視られ隔離と排除されていることが大きな問題なのです。
では「二次障害」を生まないためには何が必要なのか?
世間の間違った理解と社会的な障壁をなくすことです。
まずは世間の認識を正すこと、「特性」に応じた適切な対応と環境を作ることです。その中には学校のシステムを変えること、「特性」に合った働き方ができる環境を作ることがあります。「特性のある子ども」が特性を変えるのではなく私たちの認識と環境を変える必要があるのです。特性をなおす必要はありません。
こちらにADHDの特性のある子どもとの関わり方のヒントを書いています。
そして、環境調整ができたら「発達特性」は、武器になります。
何度も言いますが、「発達障害」の「障害」とは、本人にあるのではなく、周りの環境にあります。
だから、環境調整によって特性は素晴らしい能力になります。
特別支援教育なんかやらなくても子ども同士で助け合っていました。
「発達障害」だと診断されなくても、困った子にはお互いにできることをしていました。
枠を決めるからその内と外が生み出されます。そこから偏見や排除が生まれます。
そこにパターン化する危険性が潜んでいます。
専門家に頼るのではなく、私たちができることはたくさんあると思いますね。時代は今生きている私たち自身が創っていくものだから。
そのために、一人ひとりが安心して過ごせる学校や社会を作っていく必要があるのです。