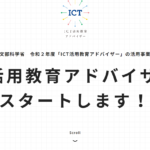発達障害の子どもの特性がわかってくると、激しい感情や行動に対処するためにクールダウン、タイムアウトという方法があります。
これは、親子関係での対処方法としてはよく知られていることですが、学級にいる感情のコントロールができにくい児童・生徒に対して教員も知っておくといい基本的なスキル(技術)の一つです。
まずは、親や教員自身がクールダウンすること、そして静かな所でそれなりの距離を置いて見守る、落ち着くまで待つことです。
子どもも大人も感情が高ぶっているときに何をしても、お互いにさらに感情を激しくするだけに終わります。このような状態の時に指示の言葉を出してもなんの効果もありません。さらに叱責して収めようとするなどは論外です。
その場限りの教員の自己満足だけの対処が少なくありませんが、このような対処方法を知っておくと、教室の中でも落ち着いた対応ができます。
その前に、「感情のコントロールができにくいのは、その子の特性なんだ。」という理解が必要であることはいうまでもありません。
それを「がまんが足りない」「集中力がない」「感情の起伏が激しくて手が付けられない」と決めつけている例が少なくないことも事実ですが。
子ども自身が感情のコントロールをするために
「自分で身に付けた方法」で感情のコントロールができるためには、さまざまな場面での練習が必要です。
家では親が、学校では教員がそのトレーニングスキルを身につけておく必要があります。
しかし、今の日本の学校では、簡単な事なのに、簡単にはできないことが問題です。
ちょっとした工夫で子どもの気持ちが落ち着くのに、下手な関わり方で逆に感情を高めてしまうことは、学校現場でもよく見るケースです。
子どもの状態によっては教員が四六時中いっしょにいる必要がある場合もありますが、子どもが自分で感情のコントロールができるようになればその必要もなくなります。
今は教員が張りついて監視する、見張るという対応しかできないために、子どもも逆にストレスを増やすことだってあります。
教員も適切な対応ができないために疲れ切っています。
親子でペアレントトレーニングなどはやっていますが、教員の多くはそれを知りません。
さらに、教室の中で感情のコントロールができる方法も知りません。
中には個人で試行錯誤しながら子どもたちと向き合っている教員もいますが、それが共有されていません。
「その教員個人」の対応スキルで留まっています。
学校や教室の環境はちょっとしたことで整備できます
「空き教室がないから難しい」というのではなく、現在の学校環境の中でできることを工夫することができればいいんです。
学校や教室の環境を整備するためにできることはたくさんあります。それもちょっとしたことです。
アメリカでは幼児の時から感情のコントロールの練習をしていて、自己の状態を客観的に見て自分でクールダウンする方法を身につけています。
落ち着かない、イライラする、感情が高まったときに自分に合った方法でできるように、学校でも練習しています。
こうなれば、「その子専用」の教員が張りつく必要はなくなり、担任ひとりで学級経営ができます。
今日本の学校で本当に必要なことは、こういうことなんだと思います。
子どもを信じて適切な対応をしていくこと。そうすれば主体的な子どもが育っていきます。
「自分で身に付けた方法」で感情のコントロールができる子になります。
だから、親も教員も適切な対応の仕方を学び、「こんなときは、こうするといい」という対応の仕方の引き出しをたくさん持つ必要があります。それができてはじめて、多様で柔軟な対応ができるようになります。
教員養成や教員の研修会でやるべきことは、これなんですよ。
感情をコントロールできない子どもへの接し方
倉吉で行われる6月10日、11日のぴっかりさんの実技講習会では、このような実践的な子どもとの接し方も学べますよ。
「感情をコントロールするために必要な訓練」や「感情をコントロールできない子どもへの接し方」も参考になります。
急に怒り出す!感情がコントロールできない子どもの対処法は?
でも、だって、そんなこと無理!
って親が思うかもしれませんが、これも基礎知識として知っておくといいですね。
キレやすい子供の原因とキレさせない8つの方法&発達障害
感情のコントロールができない子どものための5トレーニング