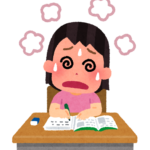今日は、鳥大医学部で行われた「子どもの心を支える支援者スキルアップ研修会」に参加してきました。
講師は近畿大学附属病院心身診療科の村上佳津美医師です。
今回は、不登校児童生徒の現状と医療機関での対応、家庭や専門機関との連携についての話を聞きました。
これまでに、発達障害に対する医療的なアプローチについては学ぶ機会があったのですが、不登校児童生徒への具体的な対応方法を聞いたのは初めてだったので大変勉強になりました。
不登校傾向にある子どもは、初期に身体的な症状を訴えることが多く小児科外来も多くなっているということで、毎日大変忙しくしておられるとのことでした。
今日は、その中でも「起立性調節障害」と「過敏性腸症候群」についての説明と対応方法について詳しく聞きことができました。
中学校1年生の男子の事例を通して、どのような対応をしてどのような経過をたどったのか具体的で分かりやすかったです。
今日の参加者は県内の小児科の医師や学校の教員など教育関係者が多かったのですが、日本小児心身医学会の小児科医向けの「不登校診療ガイドライン」と「心理社会的関与に応じた治療的対応の組み合わせ」について、医師としてどのようなアプローチをしているか丁寧な対応方法を知ることができました。
そして、本人と家族(家庭)、医療(特に小児科医)、教育機関(学校)との連携について、それぞれの立場を守ることの重要性、お互いに立場の違いがあることを分かって連携していくことが重要だと再確認できました。
今日の内容については、12月の不登校の親の会などでもお伝えしていきたいと思っています。
このようにいろんな方とつながりができると支援の輪も広がっていくと思います。
村上先生による不登校の早期対応については、日本小児心身医学会のホームページにも載っています。
http://www.jisinsin.jp/detail/16-murakami.html

子どもの心を支える支援者スキルアップ研修会に参加
投稿日:
執筆者:azbooks