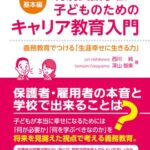私も児童精神科医の吉川徹医師と平田さんの考え方には同感です。
「発達障害を根治するために必ず医療を受診しなければならない、という状況ではない」
「医師免許さえあれば、児童の発達に係わる見識が全くなくとも「精神科」と言う肩書で営業できる」
「精神医療分野が抱える問題を、子どもたちを悲惨な状況に追い込んでいる」
どうしても医療でないとできない主な支援は、診断、特に診断書の発行と薬物療法です。
医療による支援の中には、医療でないとできないこと、医療でもできること、そして医療が得意なことはありますが、その反面医療には苦手なことがあります。
小児科医と児童心療内科医と話したことがありますが、小児科医の多くは発達障害に関する知識も理解もなく子どもたちを悲惨な状況に追い込んでいる。薬物療法は最終手段であり、その前に周囲の人の発達特性についての理解と対応の仕方を変えることで個々の子どもの状態は変わってきます。薬物療法についても、必ず「信頼できる」主治医と相談の上で適切な服用をしていくことが大切です。
発達障害の特性があるのかどうか、発達障害の特性を考慮に入れた支援が有効であるのかどうかという「見立て」は、医療機関、保健、教育、福祉などと連携して行っていく必要があります。むしろ、医療よりも教育、福祉の分野での適切な対応が望まれます。
私は発達障害の診断以上に、具体的な場面においての個々の状態に対してどのような手立てをするかの方が重要だと思っています。
発達障害は治すことはできませんが、周囲の理解と対応の仕方によって二次症状(二次障害)を防ぐことはできます。
大切なことは、発達障害の治療ではなく二次症状の予防なのです。
そのためにも発達障害の特性を理解し、個々に合った具体的な対応方法を様々な人たちといっしょに考えていくことが大事です。
現役医師が語る、発達障害と医療の望ましい関係とは?―児童精神科医・吉川徹
発達障害は治すことはできないが二次症状(二次障害)を防ぐことはできる
投稿日:
執筆者:azbooks