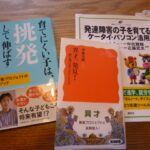10月27日に発表された文部科学省の「問題行動調査」で、「不登校の小学生2万7581人 過去最多」という発表がありました。
先日の日本海新聞では「不登校の小学生、過去最悪」という見出しでした。
私は「不登校」が「問題行動」として扱うこと自体が問題だと思うのですが、まあそれは置いといて、「不登校」についての考え方を少しじっくり振り返ってみたいと思います。
親も学校も焦り過ぎなんです
子どもが「学校へ行きたくない」と言いだしたり行かなくなったとき、少し休んでゆっくり考えてみるという時間が必要なんです。
子どもも保護者も「ちょっと学校を休んだだけでヤバいことになってしまう」とか「明日学校へ行くか行かないかどうしよう?」って、即決を迫られているようですが、ゆっくり休んでじっくり考える余裕があってもいいんじゃないでしょうか。
「明日行かなければその次がない」みたいな考え方も焦りを募らせるだけです。
また、学校側も教育委員会も「子どもが明日学校へ来ないと大変なことになる!」「なんとかして不登校の数を減らさなければ!」と考えているために、担任や不登校担当が慌ててあれもこれもと登校刺激を与えてきます。
中には脅しのような言葉かけもあります。
その反対に、どう対応していいか分からないために学校からの連絡も一切なしになって、子どもも保護者もほったらかしにされた感じを受けることもあります。
どちらも焦り過ぎなんです。
学校側も「少し休んでみてゆっくり考えてみたらいいよ。」という考え方があれば余裕ができ、今すぐどうこうしようという焦りもなくなります。
お互いに切羽詰まった感が出過ぎているためにそうなってしまうのです。
「今は休んでもうちょっとゆっくり考えましょう」という考え方でいいんですよ。
学校をちょっと休んだくらいで人生がどうこうなるということではないんです。
本当に大切にしなければならないことは何か?
「見守る」ことの本質はそこではないでしょう。
大切なことは、子どもを中心とした学校と家庭との信頼関係作りです。
日本の学校は本当に狭い範疇でしかものごとを考えられないようになってしまっていますね。
受け皿が少なすぎ、懐が狭すぎなんです。
実際にはいろいろな選択肢があります。
学校としてもできることもいろいろあります。
楽しい学校作り
生き生きとした授業作り
インクルーシブ教育
アクティブラーニング
などなど、これでもかっていうくらいいろいろなことが提案され、それをこなすことが目的となってはいませんか?
本質を見誤ってはいませんか?
もっと両者が対話を通して、子どもを中心に置いて見守ることができるのではないでしょうか。
もう少し余裕をもって子どもたちの行く道を考えていってもいいんじゃないでしょうか。
狭い範囲ではなく幅広い人たちと関わりを持つことが大切
どれだけの先生が実社会で通用するだけの力量があるのか?
子供時代からこれまで学校という世界しか知らない者なので、確かにそうだと思います。
学校教育の勉強って、ほんとうに狭い範囲でしかないんですよね。
まあ、その狭い範囲が学校というところなんですがね。
確かに、学校を休むと勉強が分からなくなるからと考えている子も親御さんもあります。
これも、これまでは子ども側の問題として放置され続けてきたことが問題です。
これは、授業内容や教え方や場の設定の問題なのです。
学校としては「分かる授業」「みんなが参加できる授業」を目指してはいるのですが、現実はそうはなっていません。
「できる、できない」「分かる、分からない」「早い、遅い」ということが学習の成果として評価される限り、この問題は解決するのは難しいと思います。
また、学校は勉強だけをしにいくところではありませんので、いろいろな子どもたちのもっている「良い点」や「持ち味」を評価していくことの方が大事ではないかと思っています。
学校だけではなく、「人にはその人に合った持ち場持ち場がある」という社会的な認識を広げていきたいと思っています。
そのためにも、限られた枠の中だけでなく、偏った価値観にこだわることなく幅広い人たちと関わりを持ちながら自分らしく生きていくことだと思います。
文科省調査 不登校の小学生2万7581人 過去最多
平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果(速報値)について