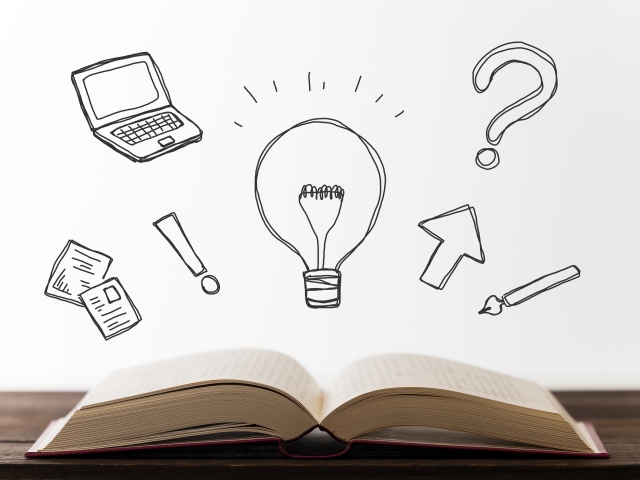
子どもの考える力ややりたいことを意欲的な学びを保障することよりも、“みんなが同じ”であることを重視するなんとも不思議な文化が日本の教育現場にあります。
園でも学校でも子どもたちが、皆一列に並んで教室に入って、皆同じように座り、そして、皆同じ内容の勉強をするように求められます。
そして先生は必死になって、みんな同じようにさせようとします。
“皆と同じ”志向が強まれば強まるほど、そこからはみ出る子どもは、“気になる子”として否応なく目立ってしまいます。
“皆と同じ”志向の教育が、独自の感性や資質を持っている子どもたちを生きづらくさせています。
みんなと同じことを求められる学校に、なかなかなじめなかった梅田明日佳くん。でも、彼は自分が興味を持ったことについて学ぶ「自学」を小3~中3まで人知れず続け、「自学ノート」にまとめてきました。
そのノートを“切符”に、少年は小さな冒険に出ます。
学び方は人の数だけあります。
学びたいことも一人ひとり違うのが当たり前です。
100人いたら100通りの学び方があります。
だから当然、評価のものさしも100個あります。
7年間の歴史がつまった”ボクの自学ノート”(NHK)
読む「ボクの自学ノート」(1)地元時計店・吉田社長との7年間の交流
読む「ボクの自学ノート」(2)安川電機みらい館・岡林館長との3年間の交流
読む「ボクの自学ノート」(3)リリー・フランキーさんら審査委員との7年間の交流
梅田明日佳の発達障害はなぜ?人格の尊重や日本の教育問題の実態に迫る!
梅田くんの作る「自学ノート」とは、どのようなもの?
梅田明日佳くんは、中学3年生の夏休みに、北九州市立文学館が募集する「第9回子どもノンフィクション文学賞」へ応募するため、この「自学ノート」の7年間をベースに、その歩みをふりかえる原稿用紙50枚の『ぼくのあしあと 総集編』を書きあげました。この作品は、中学生の部で大賞を受賞することになります。
僕は、夏休みと冬休みと春休みを心の支えとして何とか学校に行っている「どうにかこうにか中学生」だからだ」とし、小学生の時もやはり「どうにかこうにか小学生」であった。
「自学ノート」とは?
「切っても切り離せない存在です。ボクの中では、必要不可欠なものになっています。自分が今、どんなことを思っているか。以前、どんなことを考えていたか。それを見直すことができる。自分の考えをまとめるものであり、自分の心の支えでもあると思っています。」
「このノートは僕の歴史年表だ。これからも静かに僕を励まし続けてくれる」
『ぼくのあしあと 総集編』その1(PDF)
『ぼくのあしあと 総集編』その2(PDF)
梅田明日佳 ぼくの「自学ノート」











