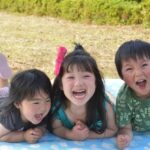毎年初日にその年のテーマを決めていますが、2023年のテーマは二つにしました。
1つ目は、2022年の「断」をさらに進めて「捨てる」「手放す」。
2つ目は「伝える」。
2022年のテーマは「断」「本気」で「断つ」
昨年は物質的なモノを新たに取り入れない、不要な無駄な情報はカットする、心身にとって不健康なことはしないなど、入れないことがメインテーマでしたが、今年は持っているモノをどんどん手放していきます。
不要な物は買わない、使わない物は捨てる。本当に必要なモノだけ残す。本当に大切な人との関係だけにしていく。
物だけでなく人間関係も含めて整理する。
昨年14kg減量した断糖、断酒を継続して心身共に身軽になることを今年の目標としました。
そして、ただ捨てる、手放すだけでなく、モノを伝える、伝承していくことも同時にやっていきます。
これまで以上に好き放題の一年に
要はイヤなことはやらない、イヤな人には会わない、自分が会って楽しいと思う人たちとの関係を続け、自分がやりたいことをやって毎日を楽しんで暮らす。好き放題の一年にするっていうことですね。
このように「捨てる」「手放す」こと「伝える」ことを通じてさらに自分らしい生き方、さらに楽しい一年にしていきます。これからも