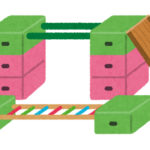平成29年度第2回いじめ・不登校対策本部会議概要には「新規不登校を生まない取り組み」について、2つ目の項目に「支援会議を核にした組織的対応のシステム作りについて」
・子どもの実態把握と支援の方向性の共用のためのアセスメントシートの作成、提案
・取組について学校への情報発信
とあります。
・「児童生徒理解・教育支援シート」を活用した組織的・計画的支援
・小・中・高と引き継ぎ支援していく体制作り
・組織的対応のシステム作り
これが全県的にどこまで進んでいるのでしょうか?
そして、学校、行政、保護者、関係者が一堂に集まって不登校を考える会が必要です。
現在の不登校対応の実態と対策について県行政にも伝えていきます。
平成29年度10月末児童生徒の問題行動・不登校等の状況について
平成29年度第2回いじめ・不登校対策本部会議、いじめ問題対策連絡協議会の概要
それにしても、県のHPから資料を探し出すのが大変です。
もっと整理して分かりやすく掲載して欲しいです。
不登校を生まない組織的対応のシステム作りが全県的にどこまで進んでいるのでしょうか?
投稿日:
執筆者:azbooks