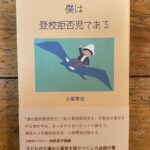学校が抱えている問題は不登校だけではありません。
学校は何年も前からとっくに限界に来ています。すでに限界を越えています。
それなのに「学校という場」をなんとか必死になって維持しようと無理に無理を重ねています。
これまでに学校を取り巻く様々な問題が起きていますが、ただ表面的に繕っているだけで問題は解決することなくますます大きくなる一方です。まるで「学校には問題がない」かのように扱われそれがないかのような日々の学校生活が行われています。これは危機意識の欠如が最大の要因であり、それが問題だと直視しないまま「学校信仰」につながっています。このような背景の下で「学校崩壊」はどんどん拡大しているにも関わらず「学校の絶対化」はどんどん進み抜本的な対策は何も講じられていないのが現実です。
では何をしたらいいのか?
まずは「学校はすでに限界を越えている」ことを自覚することです。これまでの対策は最も重要なこの自覚がないまま続けられて来たのです。
形だけ上部だけの対応に終止してきたと言えます。そして「学校という場」になじめない者、適応できない者を排除して学校をなんとか維持して来たのです。
多くの学校では「すべての児童生徒が楽しく・・・」という学校目標を掲げていますが、今はその真逆に進んでいるとしか思えません。「学校に適応できる者だけが来てもいい場」そうして「限界を越えても生き残った者」が生きられる場になっているのです。
排除や隔離ではすべての児童生徒が幸福になることは不可能です。児童生徒だけではありません。教職員の精神的疾患などによる離職者も増加の一途です。「このような不健全な環境の中で教育という行為が続けられているのが学校である」という認識を持っている人が何人いるでしょうか?
それに気づかない、気づかない振りをする、問題を認識できないままなんの手も打てないのが今の教育行政だといえます。
体力のない状態で無理を重ねていけばどうなるかは明らかです。
このままでは学校崩壊の道を進んでいくだけです。
「学校に行かない」と言える子どもがいることは健全です
私は「学校に行かない」子どもが増えているのは当然だと思っています。「学校に行かない」と言える子どもがいることは健全であるともいえます。むしろ何も考えないで学校に行っている子がいることの方が不思議だと感じています。つまり「それだけの資質」を持ち得ている者だけが行けているところが学校という場であるといってもいいです。
限界を超えているというか、学校制度、学校のシステム自体が崩壊しているといってもいいです。
崩壊しているのに無理に立たせようとするからますます立ち行かなくなっています。
その根本的な部分を無視して突破しようとしているのが今の日本の学校だと思っています。
「学びの本質とは何か?」に立ち返って学校制度そのものを直視する必要があります