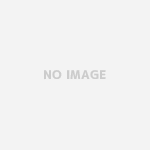親も教員もおこり過ぎています。
よくあるのが、いかりに任せて最後に「わかったわね。ごめんなさいでしょ!」と一方的に誘導して「ごめんなさい。」と言わせて納得している大人がいます。
悪いことをしたら、そんなこと言われなくても、怒られなくても子ども本人が一番分かっていますよね。
”この本はちょっとでも子どもをりかいしてもらうための本です。
まちがって子どものみかたの本と思わないでください。”
という締めくくりが素晴らしいですね。
大竹智也さんは、元フリーターで現在はラングリッチというオンライン英会話スクールの代表を務めておられます。
Web関連の書籍も出しておられますよ。
日本の教育や就労についても問題提起や提案をするなど、自ら発信して行動しておられます。
小学生のころから問題意識を持っておられたことも今につながっているのでしょうね。
小二の男の子が書いた本「おこるとどれだけそんするか?」
https://conobie.jp/article/4451
小二の男の子が書いた本「おこるとどれだけそんするか。?」
投稿日:
執筆者:azbooks