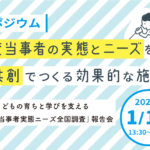学校へ行くのも学校を休むのも子どもの権利ですにも書きましたが、学校に行くには一人ひとりに理由があります。
無理をさせない。本人の気持ちを何より優先です。
親はなんとかして学校へ行かせようとしますが、子ども本人はそれをのぞんでいるでしょうか。
親が引きずってでも子どもを学校に連れていくのは得策ではありません。
この子は、学校へ行くのを渋っている。その状態について、よく「怠けている」という言葉を使うのですけど、はたからは怠けているように見えても、決してそうではありません。僕たちは必ずどこかにつまずいている部分があると考えています。そのつまずきの部分が何なのか分からないのに、行き渋る子どもをグイっと引っ張って行ったら、それは子どもたちからするとしんどいに違いないでしょう。
また、家の中が安心できない、安全な状態ではなくなってしまったために、子どもがますます外に出られなくなったり、行動を起こせなくなってしまったケースは決して少なくありません。
大切なことは「親の願い」をかなえることではありません。子どもの願いは何なのかを知り、子どもの不安を取り除くことが大切です。
親御さんも子どもを思う気持ちが強いからこそ、頑張ってしまうというのがあると思いますが、そこはぐっとこらえてください。そして、子どもは今、どんな気持ちなのかなと考え、学校に行きたくない気持ちに共感するというのが、何より大事に思います。
不登校の親はSPにならず、子を家で安心させて
・見張りタイプの親が子を放っておいたら子どもが変わった!
・友達が少なくてもいい 大切なのは子が好きなことを見つけること
・役割分担のバランスが大事。父親に限らず第三者でもいい。子育てを抱え込まず、みんなに子育てを手伝ってもらっていいという意識を持つのもよい。・
・パートナーを責めない。相手も同じように悩んでいる
1、夫を責めるな。2、子どもから離れろ。3、自分の楽しみを探せ。
・一人で悩むのではなく、第三者に相談することも考えてほしい
不登校の親はSPにならず、子を家で安心させて
不登校親の心得「子から離れ自分の楽しみ探そう」
学校へ行かせるのではなく、大切なのは子どもが好きなことを見つけること
投稿日:
執筆者:azbooks