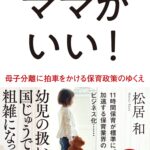今の日本の学校システムの中で、社会システムの中で、教員も児童生徒もどれだけ自己主張ができているでしょうか?
現実の政治や社会のあり方を批判的に学び考え、自身の意見を表明できる人がどれだけいるでしょうか?
次期指導要領の目玉は「アクティブラーニング」で、そういう子どもを育成するということですが、自由な意見や個性的な発想、少数意見を認め合える関係性が教室の中にあるでしょうか。
文科省の指導によって、さらに「忖度」や「自己規制」、「都合のいい解釈」や「保身のための書き替え」がはたらくのではないか。与えられた課題をこなすことと「アクティブラーニング」は真逆に位置します。
今最も求められる「資質・能力」は「批判的思考力」に基づき「自己の意見を堂々と伝える力」です。
学校が教えていない、教えることができないこと。
それは、自己決定、自己主張(自己表現)、自己責任、この3つです。
学校や社会で教えている、教わっていることは、「忖度」や「自己規制」、「都合のいい解釈」や「保身のための書き替え」です。
だから、「主体的・対話的で深い学び」をするために一番いいのは文科省の方針から脱却することです。
自由で個性的な学びを進めていくことでしか、多様性を認めたり他者を尊重する態度は育成することはできません。
どこで何を学ぶか、どこでどのように生きるかは自分が決めたらいい。
それは誰からも強制されることではありません。
どこで何をするのかは自由に選び、自分の好きなようにしたらいいです。
誰が決めるのでもない、自己決定も自己主張も自己責任も自分自身が決めることだから。
「義務」でやること「やらされる」ほどつまらないことはありません。
仕方がないからと思っているのだとしたら、そんなこといっそ辞めてしまったらいいです。
2020年、子どもの「学力格差」はこんなに広がっているかも
「ある結論に至った。
今まで私が『真実』と思っていた教科書の内容など、時の権力の意向で容易に書き換え可能なのだ。」
というか、学校とは「真実」を教えない、教えてはいけない、「考える力」「生きる力」も身につかないところだと考えたほうがいい。
ワケあり女子のワケのワケ⑤ 学校教育への怒り〜「ゆとり教育」と、見せかけの平等