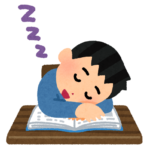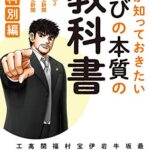『不登校』を『不幸』にしない異才発掘プロジェクト「ROCKET」が素晴らしい!にも書きましたが、中邑賢龍さんの”異能”が育まれる環境についての中で語られていることをまとめました。
不登校の子どもの中にはスゴイ才能を持った子がたくさんいる。
その子たちは既存の学校システムに合わないだけで、その才能が発揮できない。
そういう子を伸ばすためには放って置いたらいい。
好きにやれって。
好きなことを自由にやるってことは、自分のことに責任を持つこと。
その好きなことに対して、大人は徹底的に支援することが大事。
学校に行っている子どもたちは教え込まれるのがすき。
自分で何も考えなくていいから。
与えられたことをさせられるように仕向けられているから。
子どもの才能を発揮するには教え込まないこと。
学校に行っている子たちからはイノベーションは生まれない。
学校へ行っている子は社会のシステムに乗っかって生きていけばいい。
組織の中の一員として自分の役目を果たしていけばいい。
学校に行っていない子たちからイノベーションが生まれる。
既存の形から独立して自分の強みを生かしていけばいい。
だから、不登校の子が増えていることは決して悲観することでもない。
だから、どっちがいいということではない。
「不登校の特権」を生かして、自由に学び自由に遊ぼう
全く同感です。
学校に行っていない子たちからイノベーションが生まれる
投稿日:
執筆者:azbooks