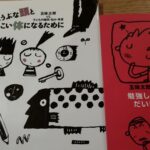そもそも「HSC」にとって、学校ほど過酷な社会はありません。大人であれば、対人関係が苦手であったとしても、それをさほど必要としない働き方を選ぶことができます。しかし、学校という場は全員が同じでなければいけないし、同じであることが求められます。そのなかでちょっとでも変わった行動をしようものなら、いじめの対象になってしまうかもしれない。「学校に適応できないなら社会でやっていけないぞ」とよく言われますが、ある意味、社会よりも過酷なのが学校という場所で、そういう集団の苦しさを誰よりもキャッチしてしまうのが「HSC」だと思っています。
社会よりも過酷なのが学校という場所で、そういう集団の苦しさを誰よりもキャッチしてしまうのが「HSC」。
「HSC」にとって生きづらい社会は、そうでない人にとっても生きづらい社会。「HSC」はこの社会を変えるきっかけになる大切な役割を担っている。
【精神科医が解説】
他人が怒られてるのに私が傷つく、ひといちばい敏感な心を持つあなたへ
学校や社会で生きにくい要因
・学校が多数派の占める外向型の子どもたち向けにつくられているから
・社会も多数派の人の在り方を基準につくられているから
「社会不適応」という言葉も多数派から見た表現であり、HSCから見たら社会の方が個に適応していないんです。
だから、「適応指導」は個人に対するのではなく、社会の側にすることが必要です。
だから、学校や社会の環境調整や関係性を良くしていくことが必要なのです。
生きづらさというのは診断名の有無で判断すべきことではありません。
診断名がなければ生きやすい、診断名があるから生きにくいというのではありません。
「障害」は本人にあるのではなく社会の側にあります。
だから、「障害」というくくりの中での支援ではなく、すべての人が暮らしやすい、生きていてよかったといえる社会を作っていく必要があります。
HSCにとっての学校