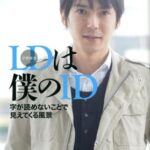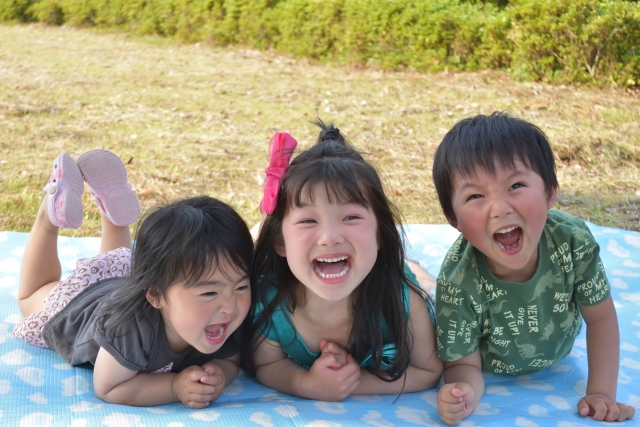
子どもには好きなことをやる権利がある。
子どもには学ぶ権利がある。
子どもには学ぶ自由がある
興味関心のあることを知る、学ぶ権利がある。
自分の好きなことを、好きなところで安心できる環境の中で学ぶ自由がある。
多様な考え方を認めるとは、多様な場、個に応じた環境を用意するということ
多様性は一斉一律の教育の中では学ぶことはできない。多様な考え方、多様な人たち、多様な環境の中で身に着けていくものである。
多様な考え方を教育することはその価値観を押し付けることになり、多様な考え方を学ぶことはできない。
自らが多様な環境の中に身を置くことでしか多様な考え方を持つことはできない。だから多様な場が必要である。
それが主体的に学ぶということ。
子どもの権利条約 不登校の子の権利条約
大人には、そのような環境を用意する義務と責任がある。
決して子どもの興味、関心、意欲を奪ってはならない。
それは、個々の好き、やりたいを実現することでしか叶えられない。
現在の日本の学校のようなスタイル、学校制度にはもう存在意義はない。
学校は学びの場ではない。
子どもにとっても教員にとっても有害でしかない。
最も大切なことは「個の自由の保障」である。
その価値、その意義に気づいた子どもたちが「学校に行かない」選択をしている。
だから「学校に行かない」という子どもたちこそ「本当の価値」を知っているといえる。
だから、「学校に行かない」ということには何の問題もないどころか、むしろ。健全な主張なんだ。
今では学校以外の場もできてはいるが、そこに「個の自由の保障」はあるか?
私には、そこは「してあげる感」しか感じられない居場所にしか見えない。
大人たちの満足のためにあるとしたら、そこもまた有害でしかない。
差別の構造を作り上げたものが「差別をするな」という矛盾

「同調圧力」が起こる仕組みを作ったものが「圧力があってはならない」という。
差別の構造を作り上げたものが「差別をするな」という。
しかも、まるでそれが「正義」であるかのように。
圧力に応じない者を排除し、差別をされたものは分断され、どんどん孤立化していく。
これは「コロナ騒ぎ」によって再び表面化しただけで、騒ぎの前から潜在的にあったこと。
「コロナ前のように正常な日常を」というが、根本的な構造を変えないと「正常な日常」などありえない。
「正常な日常」とは誰もが自由であることをいう。
誰もが自由に意思を表現できること。
誰もが自由にものがいえること。
誰もが自由に行動できること。
誰もが自由に生きられること。
それは他者が決めることではない、当事者本人が決めること。
そして、その自由を誰もが保障されること。
あらゆる束縛や支配から解放されることなしに自由の獲得はできない。