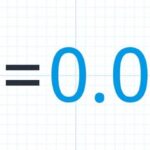不登校、ひきこもり、発達障害のある子どもさんの親御さんと話をして思うことがあります。
みなさんがフラットな関係でフリーで話をしているのですが、「学校の評価」と「教員の対応のしかた」の問題です。
教員がうまく対応できているかどうか以前の問題として、親の話が伝わっていない、伝わっていたとしても対応が遅すぎることが多いです。
学校現場が忙しいというのも確かですが、それは「言い訳」に過ぎません。
忙しいから目の前の子どもは後回しにしてもいいのか?ということになります。
お母さん方と話をしていると、あまりにも酷過ぎる対応が多すぎます。
中には個人の誠意と努力をして熱心な教員もいますので、運よく「いい先生」に”当たった”子どもさんはいいのですが、そうでない教員ばかりの学校では、子どもは追い詰められて行き場を失っています。
そんな学校環境が「二次障害」を引き起こしているといってもいいです。
「一次障害」の理解がないまま子どもに強制し、追い詰める、その結果「二次障害」というケースも少なくないのです。
さらに、子どもさんをなんとかしたいという思いから親御さんも悩んでおられます。
それを解決する1つの窓口が学校なんでしょうが、その窓口が閉じられているのではどうしようもありません。
これは、他の県の問題ではなく、あなたの子どもさんが通っている鳥取県内で起きている問題です。
教員個人の努力にも限界がありますので、システムとしての学校体制作りが急務です。
教員だけではできないこともありますので、そこは保護者とも連携していけば光も見えてきます。
まずは、何でも言える関係作り、誰もがいつでも気軽に学校に入れるようにすることが先決です。
そんな悩みを持っておられる親御さんのために、鳥取県内でも「親の会」があります。
明日10月17日(土)は鳥取たんぽぽの会に参加してきます。
グレーゾーン・発達障害 二次障害で親子とも苦しまない為に
http://mamasola.net/?p=24614&fb_action_ids=792085957521521&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map=%7B%22792085957521521%22%3A794144097275629%7D&action_type_map=%7B%22792085957521521%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
不登校は「学校の評価」と「教員の対応のしかた」が問題
投稿日:
執筆者:azbooks