
今の日本の教育の問題点は様々あります。
誰が考えても理不尽な校則、「見映えがある」儀式や「見せる」学校行事のための何回も何回も繰り返される
練習、軍隊のような集団行進、応援団を中心とした上級生の指導による応援歌練習。
その一方で、校則や定期テスト、通知表のない公立学校もある。
そんな「なにか、学校って変、おかしい」と気づいている人はたくさんいる。
しかし、そんな「おかしい」をなぜ変えることができないのか?
「なにか、おかしい」と気づいている人は身近にも多くいる。 教員の中にも、個より集団を重んじる学校に疑問を持ちながら、日々の多忙に忙殺され、「教員だから」という特別意識に縛られて、何も言わない、身動きできなくなっている人たちがいる。「集団に同調する学校教育」を受けた人たちが大半を占める世の中になれば、誰もが生きづらい社会になってしまう。恐ろしい社会になってしまう。
だから、「おかしいことはおかしい」と言わなければなりません。「おかしい」と気づいた人と一緒に声を上げていく必要があります。
何も言わなければ何も変わらない
おかしいことは「おかしい」と言わなければおかしいまま何も変わらない。
おかしいことがおかしくないことになってしまう。
おかしいことにおかしいと気づかなくなってしまう。
誰も「おかしい」と言えなくなってしまう。
おかしいことを「おかしい」と言った者がおかしいとされてしまう学校という組織はやっぱりおかしい。
そんなおかしなことを強制している学校という組織、学校システムはやっぱりおかしい。
私がなぜ教員を早期退職して今の活動をやっているのか?
途中で辞めないで教員を続けていたら死んでいたかもしれないからです。
自分の健康と命を守ために辞めました。
「学校が理由」で子どもも教員も自殺している。
それが一向に止まらない。
子どもや教員が亡くなっても何ごともなかったように日々が流れていく。
まるでそれが当たり前のように、メディア報道を見て子どもや教員の自死を日常茶飯事のごとく感じて、まるで麻痺しているように思います。
本気で変える気がない形だけの対応
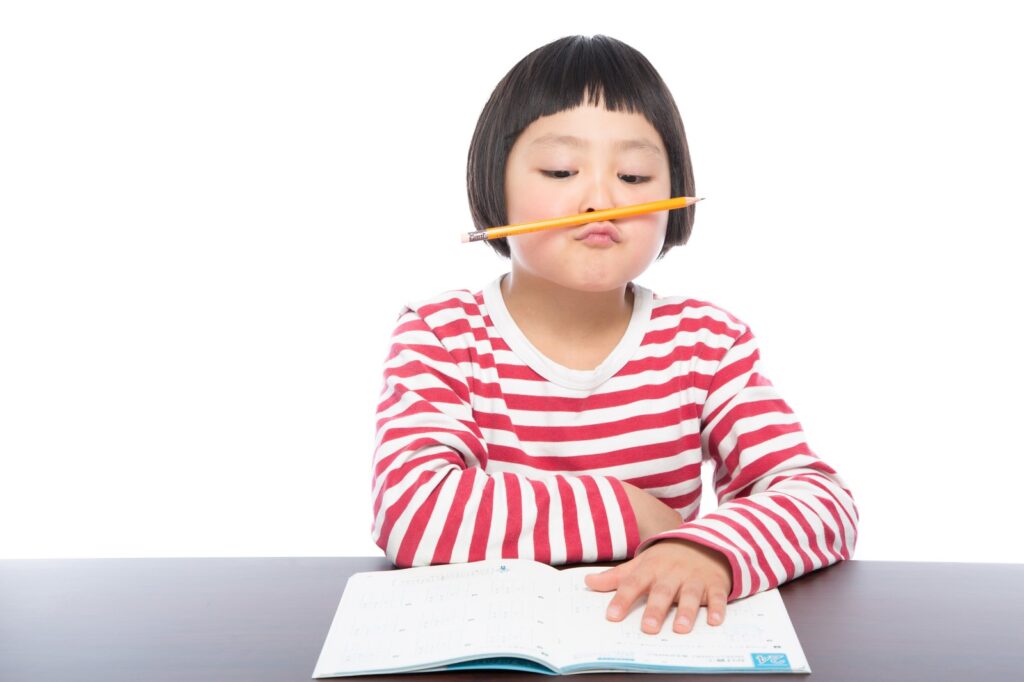
そして何か学校で問題が発生すると、毎回毎回同じような謝罪会見と「再発防止」という「言葉だけ」「カッコだけ」の繰り返し。まったく具体策がないまま人々の記憶から消えていく。
「学校が理由」であるのなら、学校を変えなければいけません。
子どもも教員もこれ以上壊してはいけない。
子どもも教員もこれ以上死なせてはいけない。
そのためには学校を変えなければいけません。
「登校拒否」は子どもの防衛反応、危険回避行動です。「自分の命を守る」行動です。甘えでもワガママでもなく、「自分の命を守る」行動です。
家庭内暴力も「自分の命を守る」行動です。その背景の多くは学校のシステムがあります。
「教育改革」とか「教員の働き方改革」という曖昧な表現を使って「長時間労働の改善」といっていますが、これは「教員の命を守る」ために絶対に必要なことなのです。
だから学校を変えなければならないのです。
子どもも教員も自分の好きなことが思いっきり時間を気にしないでできたら学校はもっと楽しくなります。
しかし、そんなところは「学校」って呼ばないんだろうな。
そのためにこれからも闘っていきます。










