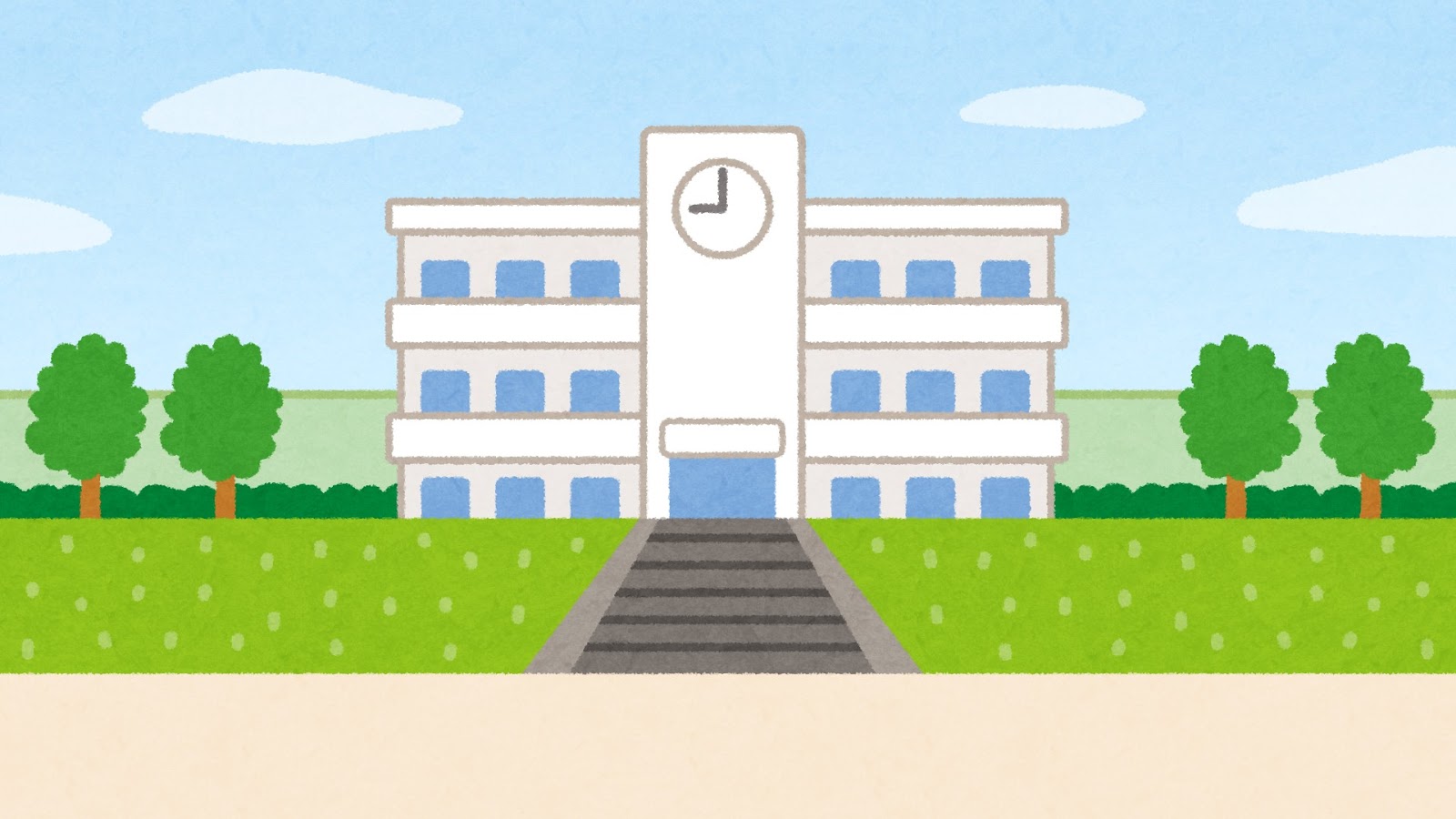
NHKの解説委員も何も分かっていません。
「教育機会確保法 不登校対策は」(くらし☆解説)
この法律をちょっと読むと、子どものことを考えているように思えます。
しかし、この法律には欠陥があります。
「休んでもよい」というのは支配する側からの一方的な命令です。
子どもがいつどこで学ぶかは本人に決める権利があり、自由です。
6歳から15歳の就学期間、義務教育期間はその年齢になったら自動的に所属校が決められ、15歳の3月には中学校卒業という「資格」が自動的に与えられます。
学校へ行っているか行っていないかに関わらず、どこにいても中学校卒業になります。
しかし、この法律はフリースクールを含む、文科省が認めていない「学校」へ行っていない子は中学校卒業「資格」はもらえません。
つまり、学校へ行っている子といっていない子が分けられるということです。
そもそも「不登校の子ども」という見方自体が間違っています。
「不登校」という概念を認めることが間違いであり、「不登校」そのものが存在していません。
「不登校の子どもたちが安心して学べる環境を作り上げる」のではなく、「すべての子どもが安心して学べる環境を作り上げる」ことが必要なのです。
不登校の子供を支援する『教育機会確保法』とは?
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日(文科省)
こちらでフリースクール全国ネットワークがこれまでに作成した資料等を公開しています。
フリースクール全国ネットワーク公開資料










