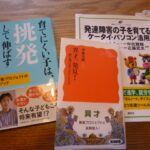今の現状を嘆いたり諦めたりするのではなく、「ではどうする?」という具体的な対策と行動が重要です。
これらの本は批判するためではなく、具体的な処方が書かれています。
『はずれ先生にあたったとき読む本』と聞いて、「あるある、うちもそうなのよ~。」っていうお母さんがいるかもしれません。
でも「当たり先生」とか「はずれ先生」って相対的なものです。
親の一方的な価値観で「はずれ先生」と思っているだけかもしれません。
「はずれ先生」にあたったと嘆くより、そのときの対策を知っておくほうが得策です。
「先生という職業」は何か事が起こったときにだけクレームを言われたり、先生のせいにされたりする仕事です。これだけ多忙の中で問題なくやっていることは実はすごいことなのですが、普通にやっていても何も言われません。それは「先生は教育のプロなんでしょ。それなら当たり前だから」と思われているからです。
しかし、何か起こると「先生なんだからどうにかしてよ!」「先生のくせにそんなこともできないの!」と言われます。
でも、先生だって人です。
言葉の使い方ひとつで気持ちも変わります。
「先生にはいつも感謝しております。」
「いつも見守ってくださりありがとうございます。」
「先生のお陰でうちの子すごく成長しました。
と言ってみましょう。
誰だって人は他者に認められたいものです。親御さんから感謝の言葉を言われて嬉しくないはずがありません。とても嬉しいものです。
特にこの学年末に伝えておくと、先生も「また新学期も頑張ろう!」」という気になって新学年のスタートも気持ちよくできると思います。
先生って、世間知らずですが、結構単純な人たちなんです。
この本、保護者研修にいいです。
『震える学校』
「いじめは、本音をいえない空気を好む。嘘や隠蔽が行われる場所を好む。教員同士のコミュニケーションのなさや、教員と親の相互不信、子どもと大人の不信感、そのすき間に入り込んでくる。」
子どもがいじめを受けても大人に訴えない大きな一因は、大人への信頼が失われていることです。保護者と教員の間が相互不信に陥っていると、たいてい事態は悪循環します。両者が相手のせいにする傾向が強いので相互に責め合っていては事は解決することは不可能ですから、第三者の介入が不可欠です。しかし、第三者委員会は「第三者」で構成されているのではなく「学校側の内部関係者」で占められていることが、まず大きな問題です。
『震える学校』の第3部にはその具体的な処方箋が書いてあります。できれば教育委員会で一括購入して、すべての教職員室に備え付けて読んでもらいたい内容で、ぜひ教職員研修で使うといいです。それが無理なら自費で買って自己研修してほしいです。
「当たり先生」も「はずれ先生」も学校教育に携わるすべての人たちへ読書のすすめ
投稿日:
執筆者:azbooks