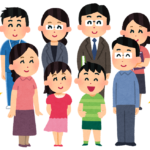いよいよ2学期がはじまりますね。
私もこの時期が1年の中でもっとも嫌な季節でした。
1学期に学校に行っていなかった子へは夏休み中も学校から何らかのアクションがあったかもしれませんし、始業式を前にして校長や担任から連絡があった家庭もあるかもしれません。
それに対する受け止め方は様々だと思いますし、学校との関係にもよりますが、子どもも親も学校からの連絡ほど嫌なものはありません。
学校へ行っていないからといってどうってことはないのですが、連絡があればあるほど、学校へ行っていない罪悪感が強くなります。
不登校のときは学校復帰だけを目的としないにも書きましたが、「学校復帰だけを目的」とした声掛けはますます子どもを追い詰めることになります。
「不登校対応についての教職員研修資料」などには、「ありもままの姿を認める」とありますが、そうなっていません。
学校としては学校復帰にこだわっていますし、不登校の人数を極力減らすことが正しいと信じて疑いません。
教育委員会への「いい報告」も仕事のひとつなので、数字を減らしたいというのが本音です。
不登校対応の問題点ついては、鳥取県 不登校の理解と支援のための教職員研修資料の問題点や「不登校児童生徒への支援に関する最終報告」って本質の理解ができていないにも書いています。
しかし、どのタイミングでどう行動するかどうかは本人が決めることです。
また、いろいろなところで居場所作りも行われていますが、まずは家庭内で安心して過ごせることが最も重要です。
子どものありもままの姿を認める、信じて、見守り、待つこと。これは親はもちろん、学校関係者にもいえることです。
学校へ行くのがつらくてつらくて苦しんでいる子が「学校へ行きなさい」「学校に来なさい」といわれることで、ますます自分を追い詰めることを知ってください。
「今」は、親御さんも先生も他にもっと大切なことがあるのです。
「見守る」とは、100%子どもを信用すること。大人の世間体や都合は1%も入れてはいけません。
それが、子どもを信じて見守るということです。
2学期を目前にして、親御さんと学校の先生へのメッセージを書きました。
「学校へ行くか行かないかは自分で決めたらいい」親御さんと学校の先生へ
大切なことは子どもの「心の安定」です
学校に行くのがつらい子は無理して学校に行かなくてもいいよ。親御さんも無理して行かせなくてもいいです。学校の先生も無理して来させなくていいです。
子どもがどのタイミングでどう行動するかどうかは本人が決めることです。学校に行く行かないの決定権も子ども自身にあります。
大切なことは子どもの「心の安定」です。「今の子どもの気持ちの安心感」です。
学校がつらい子に無理して学校に行かせることが子どもの心の安心になると思いますか?
それを考えたら親がすること学校が何をすべきかは分かるはずです。
だから、今の子どもにとってはまずは安心して過ごせることが最も重要です。
そして、よく「子どもが学校に行かないと言い出したらその理由をきちんと聴いてその思いを受け止めましょう」といわれます。これも確かにそうなのですが、これは「今すぐに」にやらなくてもいいです。むしろ「学校に行きたくないという今」聞くべきではありません。声をかけるとしたら、「そう。じゃあ今日は家でゆっくりしたらええから、学校には休むって連絡しとくね。」と伝えるのがいいです。ここで「どうして行かないの?」とか「なにか理由があるの?」などと聞く必要はありません。学校へ連絡して担任から欠席理由を聞かれたら「ちょっと体調が良くないので今日は様子をみます。」とだけ伝えておけばいいです。
子どもの心が安定したら子どもの方から話します。「今やるべきこと」は子どもが安心して過ごせることです。その方法のひとつが親や学校にその理由を伝えなくても安心して学校を休めることです。
学校へは行きたくない、家の中にもいられない。もしそうだったら、「そのまんまで」うちへ来たらいいよ。