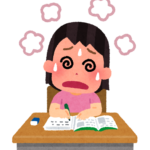iPadを使うというのは一例です。
夏休みのうちに学校と話し合いをして、1学期の様子を振り返って2学期に向けて具体的な学習方法や支援体制についてきちんと決めておきましょう。誰が、いつ、どこで、何を使って、どのように、何をするかスモールステップで「具体的に」決めることです。
その際は、学校のカリキュラムに合わせるのではなく、子どもの「得意なこと」「好きなこと」「興味のあること」から「今できている方法」やiPadなどの「使えるツール」を使ってアプローチしていくことが重要です。
少しずつ「できること」が増えることによって自信がついて「楽しく」学習に向かうことができるようになります。
「できない」のは「やる気にならないこと」を「できないやり方」や「使えない方法」で無理にやらせているからです。
それができるようになるための「合理的配慮」を考える話し合いが支援会議です。学校の一方的な要求や言い訳を聞く場が支援会議ではありません。
iPadは子どもの未来を拓く!
合理的配慮で、どんな子にも広がる可能性
iPadは子どもの未来を拓くのか?
投稿日:
執筆者:azbooks