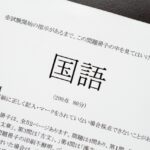昨日は、不登校の子どもと親の会「倉吉トトロの会」が倉吉市文化活動センター(リフレプラザ)でありました。
トトロの会のいいところは、参加しているお母さんが明るく元気だということです。
世話役のお母さんたちの子どもさんはすでに就学年齢を過ぎておられますが、今も楽しく活動を続けておられます。
不登校の親の会というと、悩みを抱えた親御さんの集まりということで暗いイメージをもつかもしれませんが、トトロの会はとても和気あいあいとした楽しい会です。
もちろん会の中には涙顔で話され、それを真剣に聴く参加者の姿があります。
みなさんが、子どもさんのことで同じ悩みを体験された方ばかりなので、同じ思いが分かり、自分のこととして受け止めてくださいます。
他の方の体験を知ることで、わが子への対応のヒントをもらって帰っていかれます。
そして、昨日は「わが子が不登校だった経験があるので、自分の体験を今悩んでいる親御さんに話して少しでも気持ちを軽くしてもらえたら」というお母さんも来られていました。
「もしもうちの子が不登校になっていなかったら、いろいろな気づきも得られなかった」というお母さんもありました。
さらに、小中学校で不登校だったという青年とそのお母さんも来られていて、親の覚悟も必要だと話されました。
特にお母さんは「学校に無理に行かせなくてもいい」思いと「でも学校には行かせた方がいいんじゃないか」という思いで葛藤されています。
そういう思いを整理するためにも、トトロの会のような子どもと親御さんの「居場所」は貴重な場です。
県内各地に教育機関や相談機関があるものの、なかなか本音が出せないことが多いのですが、トトロの会では、学校の対応に対する意見や自分の弱さも全部吐き出して話し合いが進んでいきます。
さらに、「多様な教育機会確保法案」についても話題になり、その問題点についても意見交換しました。
私は個人的に相談を受けている方がありますが、子どもが不登校で誰にも相談できなくて悩んでおられる親御さんはたくさんおられます。
「倉吉トトロの会」のような不登校の子どもと親の会は、鳥取県内各地にありますので、一度問い合わせてみてはどうでしょうか。
子どもが不登校になったことで、周囲の人から心無い言葉を言われることも少なくありません。
一人で悩んでいても八方ふさがりになってますます孤立していくばかりです。
「倉吉トトロの会」のような親自身が安心していられる居場所(人と場)があることも子どもの安心につながります。
当事者の会というのは、「受け入れてもらえる、共感してもらえる人たちがいる」という安心感を得るために最適な場だと思っています。
参加者同士で話をしていくうちに「大丈夫なんだ。
心配しなくてもいいんだ。
」という考え方に変わり、参考になることは家庭で行ってみたりすることで、親子で生き方に自信ももてるようになります。
いろいろな人と触れ合って広い視野で物事をとらえたほうが解決に導きやすいし、親自身も楽になれます。
「かつて不登校だったけど、今は自分で決めたことをやっている」という嬉しい報告も聞くことができます。
メッセージをいただけましたら、個別にご案内いたします。
子育てで悩んでおられる方の参加も大歓迎です。
不登校の子どもと親の会「「倉吉トトロの会」2月の定例会
日時:2月27日(土)14時~17時
場所:倉吉市文化活動センター(リフレプラザ)1階第2活動室
参加費として、お茶菓子代300円をいただいています
※途中参加、途中退場も自由です。
※話されなくても、聞くだけでも大丈夫です。
※会の終了後には個別の相談にも対応しています。
鳥取県中部の不登校の子どもと親の会「倉吉トトロの会」2月の定例会
投稿日:
執筆者:azbooks