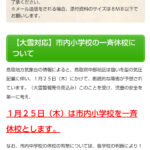自立とは独りで頑張ることではなく、依存先を増やしていくことです。
決して独りで生きていくことではありません。
頼れる人を増やしていくことを自立といいます。
自己肯定とは「できる自分」「いい自分」だけを評価することではありません。
自分の好きなこと、得意なことだけでなく、苦手なことや悩んでいる自分も含めて自分を受け止めることです。
トータルで「僕ってなかなかいいいよね。僕って結構いいじゃん。」と思えることです。
そして、学校に行く行かないで子どもの価値が決まるわけではありません。
学校に行こうが行かないが、その子はその子です。
それで子どもを評価していることが間違いです!
というか、学校であらゆる場面で一方的な評価をしていることが子どもの個性や能力をつぶしているといえます。
だから、自分のやりたいことがあるならやったらいい。
やりたくなければやらなければいい。
行きたいところがあったら行ったらいいし、行きたくなければ行かなければいい。
「そんなこといって、子どもを甘やかせてるだけ。将来どうなると思ってるの?」という人がいます。特に教員に多いですが、私はそうは思いません。
子どもが自己主張していることに価値があるのです。自分の意思を伝えていることが素晴らしいのです。
将来のために今を我慢することなんかありません。
その結果がどうなるかではなく、今自分がどうしたいかの方が大事なんです。
今は今しかないのだから、自分の気持ちに素直になるのが一番大事です。
空気を読まないで、思いっきり自分のやりたいことをやったらいい。
不登校、いいじゃないか。
「自分のすべきことについて自分で決定する」ことを認められるかが、大人に問われていますね。
これからもそんな子どもたちを応援していきます。
増加する不登校、自己肯定の場を
学校に行こうが行かないが、一人ひとりに価値があります
投稿日:
執筆者:azbooks