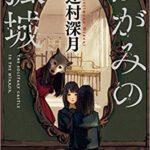以前は自閉症や発達についてばかりを勉強していた。もちろんそれはそれで今でも大事だと思っているし、自分の実践の基盤にある。
ただ、発達障害のあるお子さんと多く関わるようになってから、二次障害の問題について、理論だけで彼らの実態を分析することに難しさを感じるようになった。二次障害は複合的なものだからだ。仮説だてをしようにも、実践に失敗が許されない場合がある。特に触法少年や不登校児。
理論派の人から見ると「胡散臭い」と思われるだろうし、わたし自身も数年前まではそちら側の人間だった。ただ、いざ当事者の立場にたってみると、叙述でしか語れないことが多くあると思う。
「本当に必要な支援とは ~ 見方を変えてみる」
https://www.manabinoba.com/index.cfm/8,23277,21,195,html
二次障害は、そのまえに一次障害の理解不足があります。
さらに、周囲の環境作りや学校での対応のまずさが要因になっていることは確かです。
一次障害のついての知識・理解はもちろん、本人の状態の理解の元で適切な対応ができていれば二次障害を生むことは少なくなるはずです。
「こうあってほしい」という立場や想いで一方的な考え方をしているのは教員だけでなく、親御さんにもあるのではないでしょうか?
本人不在の支援計画、しかも学期初めに作ったものの見直しがされていないこともあると聞いています。
教員や親御さんは早く「答え」を出したいという思いが強いので、形を整えたがる気持ちはよくわかります。
子ども本人がいい方向に向かっていくのが目標なんですが、教員や親御さんが満足できたかどうかで決められるのは意味がありません。
教員の都合や親御さんの願いだけでなく、子どものニーズを知ること、子ども本人が「どうしたいのか、こうなりたい」ということからスタートしなければなりません。
そのためには、吉田さんの仰るようにやはり、まず第一に子どもとの信頼関係作りが大切です。
早急に支援計画のような「答え」を求めるのではなく、本人の自己決定ができるように支援していくことがはじまり、ファーストステップなんだと思います。
特別支援学校でも通常の学級でも教員の多忙化はますます激しくなっていることも事実で、一人ひとりに対応しきれていません。
教員個人の努力だけでは限界に来ているともいえると思います。
ですから、思い切った仕事内容を精選、バッサリと切ることは切る、やめること、そして人的な配置も不可欠だと思います。
それと同時に、二次障害の大きな要因になっている社会的障壁を除去する努力も必要です。
と、さまざまな課題はありますが、それぞれの立場でできることを精一杯やっていくことでよりよい方向に向かっていくと思っています。