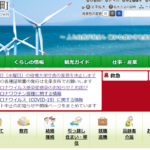NHK発達障害プロジェクトの表題にある「誤解」という表現はちょっと違うと思います。
「誤解」ではなく「無理解」と言った方が近いと思います。
最近は障害の中でも特に発達障害がクローズアップされていますが、「普通であること」「みんなと同じであること」を求めているのは、障害者自身でもあると思います。
「普通でないこと」によって、障害者本人も劣等コンプレックスを増やし自尊心を失わせている。
それは、周囲の無理解や偏見などの社会的な障壁によって引き起こされている自己認知なのですが、やはり「発達障害」という言葉にもマイナスを生む大きな要因を含んでいると思います。
ただ、「発達障害」という「診断」を受けることでホッとするというのも確かにあると思います。しかし、「障害名」を知ることによってさらに自分を追い込む場合だってあります。
それは個々の受け止め方や意味づけによる「差」なのだとも思いますが、どうしてもネガティブに受け止める傾向が強いです。
実際に書類を出す窓口で「文字が書けないので、代わりに書いてください。」、よく聞けなかったので「もういちどゆっくり話してください。」とはなかなか言えません。
自分が「普通でない」と思っているのでは、「できないのは自分のせいだ」「頑張りが足りないからだ」と思ってしまうのも至極当たり前のことだと思います。
「できないこと」「書けないこと」を隠したい、他人に知られたくないという気持ちが出てくるのも当然のことだと思います。
それを正しく認識するためには、他者評価による自己認知を変える必要があります。
「普通」というあいまいなもの、存在しないものにみんなが支配されています。
「普通」を絶対神のように信仰していることに気づき、考え方を変えていく必要があります。
・障害は本人のあるのではなく周囲の環境にある
・個々の持っているのは障害ではなく「特性」であるという強く広い認識
さまざまな困難は環境を変えることで困難ではなくなります。
そのために、さまざまな「特性」を持った個がいろいろな方法で伝えています。
それは「特性」を持つ当事者にしかできないことであり分からないことです。
さらに、「発達障害」というカテゴリーに特化して考えるのではなく、「特性」に焦点を当てて見ていく必要があるのではないか、と最近特に感じ始めています。
障害があるからどうのというのではなく、目の前に困っている人がいる。そのとき何をしたらいいのか、何ができるのかということなんです。
その場ですぐにできることもあれば、準備が必要なこともあります。
法律で「合理的配慮が義務づけられた。」だから「配慮をしなければならない。」のではないのです。
「診断」を受けることは自分の特性を知るためのひとつの手段にすぎないのであり、暮らしや学習の具体的な場面で、「その困難」にどのように対応していくかの方が重要です。
そのためには、本人も周囲の者も不器用であってもお互いの関係作りや対応経験を積み重ねていく他ないのではないでしょうか。
障害者と関わる場合に緊張したり躊躇したり、下手な対応をしてはいけない、失敗してはいけないという「遠慮」もまた「障害」のひとつだといえるのではないでしょうか。
その意識を変えていくには、お互いがもっと気軽に関わり合える関係性を作っていくしかないのです。
くらしの中では、障害者が社会のあらゆる場面で差別されている事例は後を絶ちません。
就労における「障害者枠」自体が差別事例の一つではないでしょうか。
働き方においても障害に目を向けるのではなく、「その人」のできること、能力に目を向け「自分らしさ」が発揮できる場を作っていく必要があります。
まずは知ること、学びも大切ですが、身近なところでの具体的な行動にかかっていると思います。
それを知って、自分なら何をしていくか考え、具体的な行動にどう結び付けていくか、一人ひとりが自分の環境を変えていくこと、そしてそれをつなげて広げていくことによって社会を変えていくことができます。
思いではなく、具体的な行動によってしか差別意識をなくすことはできません。
NHK発達障害プロジェクト「みんな発達障害を誤解してます!」
障害者と関わる場合に「失敗してはいけない」という遠慮もまた「障害」のひとつです
投稿日:
執筆者:azbooks