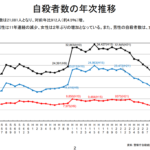生きることは評価されることではない。
「褒めて育てよう」という人がいるが、褒めることは、上手い下手、勝ち負け、出来不出来など、他者に優劣をつけて評価すること。
親が子どもに、教員が生徒に、上司が部下に優劣をつけて評価することだ。
みんな一人ひとり違うのが当たり前なのに、無理矢理同じ土俵にあげられて基準を決められて優劣を判定される。
これでイジメが起こらないはずがない。差別が生じないわけがない。
学校という場所は本人は求めていないのに、常に他者評価される。そしていつの間にか「よい評価」を得ることが生きる目的になってしまう。それが死ぬまで続いていく。
私たちは産まれた瞬間からそんな評価の中で生かされている。
生きるために必要なことは褒められることではない。無条件で他者に共感してもらうことです。
新年度、学校生活に違和感を感じている子どもたちがいると思います。
新入社員として戸惑っている人もいると思います。
あなたの感じた違和感や戸惑いは正しいよ。あなたがそう感じることは間違っていないよ。
自己満足がいちばんいい。
わがままにテキトーに生きるのがいちばんいい。
それに共感してくれる人は必ずいるから。
「勝ちと負け」
東京オリンピックは開催方向のようだが、アスリートからの発言は皆無に近い。勝ち負けという世界で生きてきた人は、勝ち負けで自分を評価する癖が付いている。
評価の対象がないことは、アスリートにとっては自分の存在価値の否定にも繋がることだと言っていた友人もいる。
勝ち負けが全てではないのは、誰もが知っていること。なのに人は様々な面で勝ち負けで評価し、自分の価値を見誤ることで、人生を翻弄される。
足が速い人が憧れの存在であり、いつも百点を取る生徒が先生から評価される。学校という思想的な団体の中で幼い頃を過ごせば、当然、そのような間違った価値観で生きることになる。
大人になっても評価に引きづられる。役職や職業や収入や、下手すれば車やバッグの価格で評価してしまうのだから、なんとも悲しい価値観である。
勝ち負けはイジメにも繋がる。Twitterはイジメの構図で成り立っている。目立つ者を攻撃する事で、自尊心を守る。自分が目立たないことが敗北だと捉えるからであろう。
僕は人を評価しない。講座の生徒であっても決して評価しない。僕が評価したところで、単なる個人的なレッテル貼りにしかならず、褒められても褒められなくても、生徒の知識力アップには繋がらないのを知っている。
褒めて育てるというのは、僕は懐疑的である。叱って育てるのが良くないのは事実だが、褒めるということは勝ち負けを意識させることでしかない。上手く行こうが失敗しようが、本人がどう思っているかが大事で、必要なのは同意なのである。
生き方に勝ち負けなどない。どんな人でも苦しみ、悲しみ、悩んでいる。その反面、どんな人でも喜び、感謝し、人を愛している。それだけでいい。それだけで十分なのである。
自分を評価することを手放してみよう。すると、他人と比較することが馬鹿馬鹿しくなってくるはずである。自分がやりたいことを、ただひたすらやればいい。評価から解放されると、必ず幸福に生きられる。
所詮、人生なんてそんなものだ。あ、おはよう。