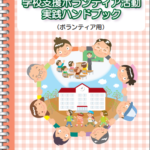国がこれから開発するというオンライン学習と新学習指導要領の「カリキュラム・マネジメント」と矛盾していないのでしょうか?
文科省は、小中高校生の「家庭学習の充実」に向け、パソコンやタブレット端末を使って出題、解答するオンライン学習システムの開発に乗り出すとのことです。今年度中に実証研究に着手し、将来的に教員が作問・出題から成績評価まで活用できる環境づくりを目指すとのことです。
「国主導」でシステムを開発し、感染症の蔓延まんえんや大規模災害が発生した際にも「自宅や避難先での効率的な学習を可能にしたい」。
問題は、過去の出題蓄積がある小学6年生と中学3年生が対象の「全国学力・学習状況調査」(全国学力テスト)をベースに、国立教育政策研究所などと協力して拡充する予定のようです。
【独自】オンライン学習、国が開発へ…作問から成績評価までの活用目指す
なんか、ようわかりません。
文科省の通知を読めば読むほど、取り組もうとしていることを知れば知るほど、さっぱり分かりません。
新学習指導要領の柱「考える力を育てる」ために最も必要なことに書いたように、新学習指導要領の3つのキーワードは「資質・能力」「カリキュラム・マネジメント」「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」です。
カリキュラムマネジメントとは、各学校が教育課程(カリキュラム)の編成、実施、評価、改善を計画的かつ組織的に進め、教育の質を高めることです。新しい学習指導要領が目指すのは、「授業の質的転換」で、その中でも重要となるのが「どうやって子どもたちに主体性を持たせ、深い学びを実現するか」です。
子どもたちや地域の実情に合わせた教育課程を編成するもので、実現すれば個性豊かな学習スタイルをめざしていくものです。
これによって、学校での学び方が変わると期待していたのですが、文科省はどこをめざしているのでしょうか?
コロナのために、新学習指導要領のいう主体的・対話的で深い学びのためのカリキュラム・マネジメントは吹っ飛んでしまったのでしょうか?
このオンライン学習システムで新学習指導要領の目指す教育を構築するのでしょうか?
このシステムを元にして「カリキュラム・マネジメント」する、カリキュラムを作るのでしょうか?
それとも、このシステムは「家庭学習用」に作るのでしょうか?
この内容がどういうものになるのか分かりませんが、これで主体性を持たせ、深い学びを実現できるのでしょうか?
教員の役割はどうなるのでしょうか?
これはこれ、あれはあれなのでしょうか?
学校は学校で勉強し、家庭では家庭でやるということなのか?
文科省のやることはさっぱり分かりません。?だらけです。
今、学校現場では新しい教育課程に元づいて、各学校ごと、教科ごとに新しい年間指導計画を作っています。評価の仕方も変わるため、通知表も新しく作り変えています。今まさに小学校のカリキュラム・マネジメントを0から始めているところです。
この国がこれから開発するというオンライン学習で学校現場はますます混乱しそうな気がします。
新学習指導要領の扱いはどうなるのでしょうか?
今こそ「カリキュラム・マネジメント」がすべての学校で必要
中央教育審議会初等中等教育分科会 岩本 悠さんが、「今、教育に問われていること」というテーマの資料を提供しています。
休校により本当に限られた時間のなかで育てたい資質・能力を育むために、教科横断的な視点で教育内容を組織的に再配列し、必要な人的・物的資源等を地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせる「カリキュラム・マネジメント」が、今こそすべての学校で必要です。
ICTの活用は、こうした社会に開かれた教育課程やカリキュラム・マネジメントにおけるあくまで一つの、そして重要かつ有効な「手段」です。
(初等中等教育分科会(第125回)・新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会(第7回)合同会議 参考資料2 岩本委員提出資料から引用)
これまでの画一的で均一の学校教育スタイルによって、教育の機会から外され、学びの保障を受けてこられなかった子どもたちがいます。だから今こそ、一斉一律な授業スタイルではなく、多様な現場の実態に寄り添う個別の最適化された支援、個別のサポートが必要なときなのです。
文科省のやろうとしていることは、なんかようわかりませんが、「オンライン上の教室」での一斉授業配信は「勉強嫌いの子」が大量生産される結果に終わらないことを願うしかありません。
平成23年度(2011年度)すぐにわかる新しい学習指導要領のポイント(PDF)
令和2年度(2020年度)新学習指導要領のポイント
カリキュラム・マネジメント ~新学習指導要領とこれからの授業づくり~
カリキュラムマネジメントって何? 実行すれば学校がどう変わる
学習指導要領ってそもそも何?教員の仕事との関係とは