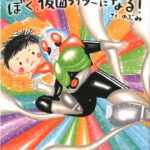そもそも一斉授業を行うことは無理。
分かっている子は授業がつまらなくて退屈し、分からない子は授業を聞いているフリをして苦痛でしかない。
これは、日本の授業スタイルが持っている本質的な問題点なのですが、それを変えようとするどころか、生徒を「落ちこぼし」ても仕方がないという考え方に問題があったのです。
そもそも同一学年で同一の学習内容を教え込み、同一の評価基準で評価することに無理があるのです。
個に焦点を当てて学び方を変えれば解決する問題なのです。
日本では、1学級最大40人の児童・生徒の集団に対して、1人の先生が一斉授業を行うというスタイルが基本だ。こういった授業でいちばん問題なのが、児童・生徒たちの学力格差が非常に大きいということだ。
とくに、算数・数学の授業でそれが顕著だ。公立の小中学校の場合、同じ年齢の児童・生徒の集団とはいっても、算数・数学における学力格差は非常に大きい。例えば5年生の児童に「円の面積」を教えるとしよう。中には、塾などで学習済みですべて完璧に理解している子もいる。一方、基礎的なかけ算やわり算さえおぼつかない子もいる。足し算や引き算さえできない子がいることもよくある。
40人近い生徒がいたが、塾で学んで完璧に理解している子たちがいる一方、わり算やかけ算ができない子もいた。わり算やかけ算はできるけど、因数分解はできないという子もいた。また、因数分解はできるけど平方根がわからないという子もいた。こういったことは、授業の指導案の個別カルテに記載されていたので、参観者にはわかったのだ。
授業についていけない生徒たちは、わからないまま座っているだけだった。一部の子たちは積極的に発言したりして、一見盛り上がっているように見えたが、その話し合いに本当についていけている子は3分の1もいなかったと思う。学力格差が絶大な中での、こういった一斉授業の「話し合い」は、生徒にとっても先生にとっても不幸だと感じざるをえなかった。
昨今こういった「話し合い」の授業が、「アクティブラーニング」という美名の下に、さらに増えてきているという実態もある。百歩譲って一斉授業を受け入れたとしても、先生がわかりやすく教えてくれるならまだしもだが、こういう子どもたち同士の話し合いを中心にした授業だと、余分な要素が入りすぎてゴチャゴチャするので、何が何だかわからないまま座っている子たちが増えるだけなのだ。
日本の一斉授業は本当にこのままでいいのか
日本の学校は、一斉授業、一律評価によって子どもたちを序列化することが目的になっています。競争に勝つことが目的となっています。
だから、こんな競争の中に落とし込まれる子どもの間からは当たり前のように差別、偏見、いじめが起こります。学校間、教員間でも序列化による排除が起こります。
学校、家庭、社会では競争して序列化することが学力を伸ばすかのように信じ込まれていますが、他者との競争による評価が学びの到達点、学びの成果ではありません。
たったひとつの「ものさし」だけで人を評価し価値づけることは、害しか生みません。
学びとは個のものです。
個々の課題があり、個々別々の「ものさし」があるのが当たり前なのです。
そうすれば競争に勝つ負けるなどという概念は存在しないのです。学びの原動力は「好きなことをする」こと、主体性を重視する環境は、競争とは無縁です。
今、「学びを止めない」「勉強の遅れをどうするか」と、日本中で必死になって焦っていますが、学びとは何かを考えれば何の問題もありません。
「通知表どうしよう」なんて、どうでもいいことです。
教員が児童生徒を評価すること自体意味がないことだから、そんなものなくしても何の問題もありません。
その考え方を基にして、いろいろなスタイルの学校をつくれば面白いことができます。そのどれを選ぶかは子ども本人です。
そうすれば、日本はもっと面白い国になると思います。
「勉強したい」と思っているのなら、やり方はたくさんある。
学校で教えてもらわないと勉強できないのなら、勉強することをやめた方がいい。
勉強しようと思っているのなら、いくらでもできる。
自分には課題意識がないのに、一方的な課題(宿題)を押し付けられ、それをこなすことが勉強だと教えられる。自分に必要ないこと(作業)をやらされて、それをこなすことが仕事だと教えられる。それをなんの疑問も持たないでいる方がおかしいと思います。
学びとは自分で課題を見つけて解決していくことをいいます。それは学校へ行かなくてもできることです。学校という枠を決めるのではなく、枠にはめない「さまざまな」学びの環境を創っていく必要があります。学校が変わらなければ、今の日本の学校システムが変わらなければ「不登校」は永遠になくなることはありません。「不登校」か「不登校じゃない」と分けることがナンセンスなんです。
「不登校」というのは「学校に行くのが当たり前」だということが前提になっていますが、「学び」を中心に置くと「学校に行く行かない」はどうでもよくなります。
暗記だけで数学を乗り切った学生の悲しい末路
「アメリカ最高の高校」は、生徒に教師のほうを向いて座らせない
数学できる子・できない子を生む算数教育の盲点
テクニックではなく、理解を促す3つのヒント