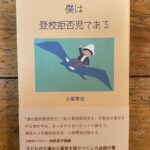どう生きるか、何を選ぶか、どの道に進むかを決めるのは本人なんです。
親のできることは、子どもの意志を尊重することです。
「学校に行かない」と決めるのも選択肢のひとつなんです。
「学校へ行くことが当たり前だ」という考え方の方がおかしいんです。
「行くか行かないか」の二者択一ではなく、選択肢を増やしていくことが必要ですね。
「学校へ行かないこと」が問題なのではなく、「行く場所がない」「行く場所が選べない」ことが問題です。
さらにその前提として、「行かないことも選択肢のひとつである」という社会的な認識と理解を広めていくことが重要です。
「学校へ行かないことは悪いこと」という社会的慣例と日本人んの認識が子どもを取りまくさまざまな問題の根源であるということを強調していきたいです。
それでも、一番強く思うのは息子の人生を決めるのは息子自身であるべきだということです。
安心して遊んだり学んだりできる環境に身を置くことが、息子が一番成長できる手段なのだと私は信じています。
レールを外れることは不安。大切なのは「どう生きるか」なんです。