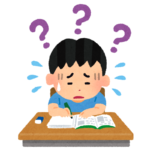学校に行かなくなった理由としては、「学校の雰囲気が合わない」から「先生がいや」だから。
学校に行かなくなった理由としては、「学校の雰囲気が合わない」から「先生がいや」だから。
こんな当たり前の理由を無視して学校側の都合だけで学校教育が行われてきました。
それどころか、文科省や教委は学校に行かなくなった理由として「本人理由」や「親子関係」をあげ、学校環境は放置したまま子どもを矯正するという誤った対応をしています。
これまで何十年も「子ども本人の声」を聞かないで学校経営をしてきた結果、「学校にNO!」という子どもたちが増えているのです。
それにも関わらず、相変わらず子どもを矯正する「学校復帰」対策をやり続けています。
・学校に行く行かないは本人の意思である。
・子どもたちが行きたい所ならなにもしなくても行く。
この2点を考えて教育環境を創ることが重要です。
学校がおかしい、学校制度に問題がある
「学校が合わない」というのは子どものやさしさだと思います。
「学校がおかしい、学校制度に問題がある」ことに気づいた子どもたちが増えているということです。
文科省や教委はそれにどう応えていくのかを何十年も前から問われ続けているということです。
「学校に行かない」といっている子どもたちは、日本の奴隷化教育、矯正強制教育にNO!といっているのです。
私もその一人です。
子どもたちは自由意志で「行かない」と決定しているわけで、「不登校」という言葉を作り上げて排除の対象にすることが目的の文科省や教委の考え方が間違っています。「不登校」という概念なんかないのです。そもそものとらえ方から間違っています。
保健室登校をしていた上白石萌音ちゃんは「メキシコでの生活が人生を救ってくれた」といいます。
変わるべきなのは子どもや親ではなく、学びのとらえ方、学校教育の在り方、学校環境なのです。
変えるべきなのは子どもではなく、学校です。
学校が変わっていかなければいけないのに変わっていないので、学校に行きたくない子どもが増えているのです。
そして、学校の他に行き場がないことも大きな課題です。
これまでのような「子どもを学校に適応させる」という対応ではなく、「子ども一人ひとりのニーズに応じて学校を変える」という発想が必要です。それと同時に、子どもたちが安心して過ごせる居場所も必要です。
これまでの不適切な「不登校対応」を反省したうえで、すべての子どもたちのために、学校制限や学校のあり方を変えていく必要があります。
宮城県内で不登校児の支援をしている団体でつくる「多様な学びを共につくる・みやぎネットワーク」(みやネット)が、不登校の子どもを持つ保護者に実態を尋ねる緊急アンケートを実施した。学校に行かなくなった主な要因は「学校の雰囲気が合わない」が最も多かった。教師の対応をきっかけに挙げる保護者もいた
学校に行かなくなった理由としては、「学校の雰囲気が合わない」が21%で最多。「先生」の18%、「友人関係」の14%と続いた。「よくわからない」という回答も14%あった。