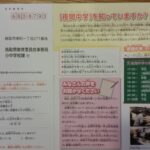主体的な学びには内発的な動機付けが不可欠です。
子どもは好奇心、向上心の塊ですから、「もっと知りたい」「もっとできるようになりたい」と思っていない子は一人もいません。
興味・関心のないことを意味もなく押し付けられ、周囲の子どもと比較されて優劣をつけられ、劣等コンプレックスをつけられる。
子どもが勉強を嫌いになるのは教える側の問題です。
教える内容や教え方がダメだから「学校の」勉強は嫌いになっていくのです。
「明日も勉強するのが楽しみだ」「勉強することが楽しい」と思って学校へ行っている教員は何人いるでしょうか?
親も「学校の勉強は嫌いでも頑張ってやるもんだ」と教え込まれているから我慢させることを強いています。
勉強とは本来楽しいものです。
教え方が楽しくさせていないだけなんです。
中2生は勉強嫌いが約6割 大規模な追跡調査で判明した「勉強が好きになった子」の特徴とは
ここでいう「勉強」とは、「学校の勉強」のことを指しています。
勉強とは本来楽しいもの、学校や教員が子どもの勉強嫌いを増やしている
投稿日:
執筆者:azbooks