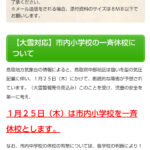全く同感です。
一般世間ではほとんど発達障害についての理解はされていないのが現状ですが、教育現場で知られていない、教員の理解が進んでいないことも大きな問題です。
教師の勉強不足や子どもの理解不足によって、学校現場で子どもたちが追い込まれています。
今日の新聞にも
”教師蹴る小1、通行人暴行=荒れる小学校、対応模索―問題行動調査”
という記事が載っていました。
ただ、これは、「文部科学省」の問題行動調査によるものだということに注意してください。
子どもや親御さんサイドからの声ではありません。
文科省の「都合による回答」であることを頭に入れて見ていく必要があります。
記事によると・・・
「小1に何度も蹴られ、教師が通院」
「登校中に注意された児童が通行人に暴行」
”低学年を中心に件数が急増しており、学校現場では対応に模索が続く。”
大阪府教委の担当者は
「家庭環境が影響し、規範意識に乏しい子どもや自分の感情を抑えきれない子どもが増えている」
「問題ある子どもに、迅速かつじっくりと対応する人の確保が重要だ」
「コミュニケーションが苦手な子が問題を起こしやすい」
と話しているとのことです。
これを見て分かるように、
「学校は対応に頑張っているが、家庭環境や子どもが悪いので困っている」
と、教委側は”問題行動を家庭や子どものせいにしている”姿が見えてきます。
大阪府教委は、他人事として考え当事者意識がまったく感じられません。
それならそれで、教育機関や医療機関、専門家を総動員して対策を講じていく必要があります。
「学校や教員の対応が悪いから」
「家庭環境も子どもの実態も変わったから」
と双方で文句を言い合ってもなんの解決にもなりません。
このままでは、ますます子どもたちは苦しみ、親御さんの悩みも深くなり、現場の教員も対応に疲れていくだけです。
熱意のある教員は本当に頑張っていますが、心身共に疲れ切っているという人も少なくありません。
このような事態への対応として、「現場は忙しいから」「人手が足りないから」という言い訳で済まされていますが、職務を精選すれば子どもと過ごしたり勉強する時間は作れます。
子どもの命と人権を守るために、教員のサポートも含めてシステムとして機能すれば、改善できることは多いです。
子どもを怒鳴ればたたくのと同じ悪影響
http://jp.wsj.com/articles/SB10001424127887323410304579064001258702132
発達障害について教員の理解が進んでいないことも大きな問題
投稿日:
執筆者:azbooks