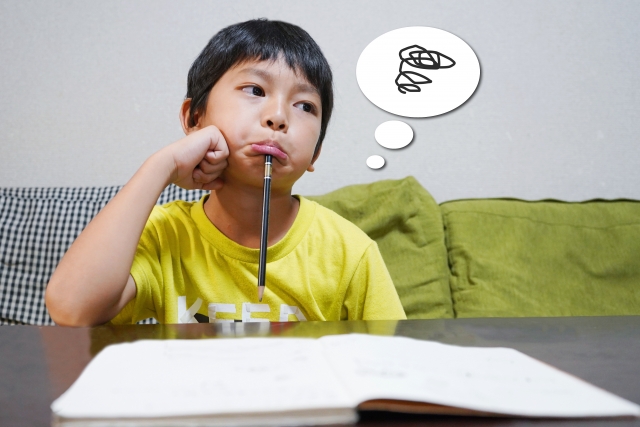
学校に行くことが必ずしも幸福とはいえない。
勉強することが必ずしも幸福になるとはいえない。
しかし、学校に行けば勉強ができると思っていませんか?
学校に行けば勉強するから安心だと思っていませんか?
確かに教室の中に居たら勉強している格好にはなるかもしれません。でも、それが「勉強」になるでしょうか?
そんな「勉強」をして幸福になるでしょうか?
「勉強」とは「教室のイスに座っていること」ではありません。
「勉強」とは、「自分で知りたい」「自分でできるようになりたい」が出発地点です。
それを「解決できるようになる」ために勉強するのです。「自分にとっての課題」を解決するために勉強するのです。
自分の「やりたい」を実現するために勉強するのです。
だから、勉強とは学校のカリキュラムとは無関係なんです。勉強するためには、必ずしも学校でなくてもいいのです。学校以外でもいくらでも勉強はできます。
教室のイスに座っていて「自分の課題」は解決できるでしょうか?達成感、満足感を感じられるでしょうか?
一方で、自分で自分の課題を解決したときの達成感はハンパないです。それは大きな自信になります。
自分でやりたいと思っていることができると幸福になります。好きなこと、楽しいことなら幸福を感じることができます。
自己解決した喜びに勝るものはありません。
幸福感は他者が判断することではなく、自分自身で感じることです。
自己満足が最高の幸福感です。
日本の学校は子どもたちに達成感、満足感を感じさせているでしょうか?
私には教員の自己満足だけ、いや、教員も自己満足感、幸福感を感じていないように、私には見えています。
働きアリや働きバチのように、言われたことをせっせとこなしているようにしか見えません。
一体誰のための学校なのか?
なんのための学校なのか?
少なくとも子どものために作られたモノではないようです。
だから、私は「やりたい!」を実現できる「自由な学びの場」21世紀の松下村塾を創りました。
一番大切なことは、「自分が何をやりたいのか」
学校に行っている子は自分で何らかの理由を持っているのですが、理由がわからないけどなんとなく行っている子もいます。
「みんなが行くから」「親が行けというから」「それなりに楽しいから」「特に理由はないけどなんとなく」という子どもの方が、もしかすると多いかもしれません。
現実として「みんなが行くから」「みんながやっているから」という理由は妙な説得力をもっています。
その目的は「卒業資格を得るため」「次の学校に進むため」「なりたい職業の資格を取るため」など「次のステップに進むため」が多いと思います。
学校の存在目的、存在価値もそこにあります。
子どもも保護者も「学校に行っていれば次のステップへのチケットがもらえる」から行っています。
でも、チケットがもらえなくなれば学校に行かない子どもが増えるかというと、そうでもないと思います。
一番大切なことは、「自分が何をやりたいのか」「自分は何を学びたいのか」ということです。
学校や社会の枠の中で生きるためにはいろいろな制約が出てきます。でも必ずしも枠の中に入らなくても生きることができます。
だから無理して枠の中に入らなくてもいいと思います。
どちらを選ぶのも自分が決めたらいいんです。
そして、いつだってその道を変えることもできます。
学校は目的ではなく「自分のやりたいこと」をするために利用する手段のひとつだと考えたらいいですね。
枠に入らなくても社会のレールに乗らなくても生きることはできますからね。
それは違うと思っていながら、「みんながやっているから」「みんなと同じだから」って、結構説得力がある理由だと思いませんか?
そして、結構「みんながやっているから」やっていることが多いです。
それはなぜなのか、「みんながやっているから」「みんなと同じだから」って、結構説得力がある理由かもしれないに書きました。
みんなと同じように要求をしているから悩む
大人たちがよってたかって「みんなと同じ」ことを求めているから苦しむんです。
「みんなと同じように」学校に行って就職してって要求をしているから悩むんです。
子どもは親の顔色を伺ってその要求に応えられないと「ダメな人間」「社会では生きていけない」と思い込み、自己否定します。
そんな考えを取り除かない限り悩みは続きます。
学校に行かないで活躍している人はたくさんいる事実にもっと目を向けように書いたように、学校に行かないでも、就職しなくても活躍している人はたくさんいます。
親のできることは、子どもが本当にやりたいことをやれる自由を保障することです。
みんながやっているからであっても自分の意思でやっているのならいいとは思いますが、やりたくないのに同調圧力に流されているようなことがないでしょうか。
場の空気を見ださないように、雰囲気を壊さないように言いたいことがあっても黙っていることがないでしょうか。
本当は断りたいのにしかたなく従っている人も少なくないような気がします。
自分の意思を伝えるようにしっかりと自己主張していきたいものです。
教研式NRT・CRT標準学力検査テストも「他の学校もやっているのでうちの学校も」「教育委員会がやれといって補助金が出ているのでやっている」という理由でやっているもののひとつです。このように、学校では無駄なことがどんどん増えています。
自ら考え主体的な子どもを育てるといっている学校がこれではどうなのか?って思います。
今の自分があることはすべて過去の自分の努力の結果
他人からどう思われるのかではなく、自分がどうしたいのか。聞いている人、読んでいる人がどう思うかではなく、自分が何を伝えたいのかなんです。
赤ちゃんのときは泣いても笑ってもみんなが喜ぶのに、大きくなるとなるほど褒めてくれることが少なくなっていきます。
すると、自分で自分の可能性を縮めてしまったり限界を決めたりしてしまいます。
日本の受験システムによって、学力テストの点数で評価される割合が多くなり、そのために勉強することが義務になります。
義務になるということは「言われたことに従うこと」が評価されるようになります。
だから、だんだん思考力と主体性を奪われていきます。
努力も「他人が見て」評価するものではなく「自分自身がやりたいこと」に向かって進んでいるかです。
それは他者との比較ではなく、一瞬前の自分との比較をすべきで、その大きさによって決められるものでもありません。
だから、今の自分があることはすべて過去の自分の努力の結果です。
学校よりも家庭での教育で学ぶことが有効な子どももいます
学校では必要とする支援がなかった、特別な支援を必要とする子や障害のある子たちの間でホームスクーリング、家庭での教育で学ぶことが増えてきています。
みんな自分らしく生きていくために学ぶのです。
学校に行くために生きているのではありません。
他人のために生きているのではありません。
自分が自分を生きるために、今ここに存在しているのです。
だから、「自分がやりたい!」がすべてです。
学校という形や枠に合わせるのではなくて自分がやりたいことをしたらいいですよ。
不登校を選び発達障害の子が家庭学習で成長










