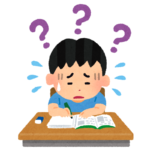不登校は生き方の選択肢のひとつ。
ネガティブな体験でもない。
学校へ行かない生き方もある。
学校へ行かなくても中学校は卒業できるし、高校や大学にはいつだって行ける。
進学しない生き方だってある。
私は教員になってから不登校を選択して、今の生き方を決めました。
学び舎 傍楽「不登校のおはなし会vol.10 特別企画開催!」
「大人の安心」のために「子どもの不安」を増やしている
50年前の当時は、「学校に行かない=病気」という構図ができあがっていて、親も、どこかに入れて「治療」してもらわないといけないと思っていた。
子どもの人権を無視した、児童相談所による強制的な児童拉致も行われていたことを知らない人も多い。
あれから50年経った今も、学校へ行かない子どもへの視線、この構図や対応の仕方はあまり変わっていない。
親も学校も「なんとか学校に行かせたい」という考え方が根強い。
「学校に来させる」ことで「教員」が安心したいのだ。「どこかに入れる」ことで、「親」が安心したいのだ。
このような「大人の安心」のために支援している専門家や専門機関も多い。
彼らは「それが子どもの幸せ」だと信じて疑わない。
これを、私は「学校信仰」といっているが、「学校へ行かない、行けない子どもたち」は、それで自分を追い詰めている。
子どもだけでなく、親や教員が「見えない不安」を感じている背景に、この学校信仰がある。
親や教員のしていることは、「見えない不安」を取り除くためにしている「大人の安心」の押しつけであり、「子どもの安心」ではない。「大人の安心」のために「子どもの不安」を増やしているだけなのだ。
親の期待に応える子どもが「いい子」ではありません。
誰に対してもちゃんと自己主張できる子どもが「いい子」です。
だから、「学校へ行きたくない、行かない」と言える子どもはいい子なんです。
ボクも、いい子でした。
私たちにできることは、学校信仰からの解放です。
早く学校信仰から目を覚まして、子どもたちを解放してやりたい。
学校に行って、給食でゆでたまごが出るかもしれないと思うだけで、ふとんから出られなくなりました。それで、「病気」になるわけです。実際に熱が出たり、お腹が痛くなったりして、いま思えば、それは「病気」がボクを守ってくれたんだと思います。そのおかげで学校に行かないですむ。
でも、その代わり、精神科医や児童相談所に連れていかれました。学校に行かなくなったのは5年生になってすぐでしたが、5月には明石の児童相談所の一時保護所に入れられて、2カ月ほどいました。