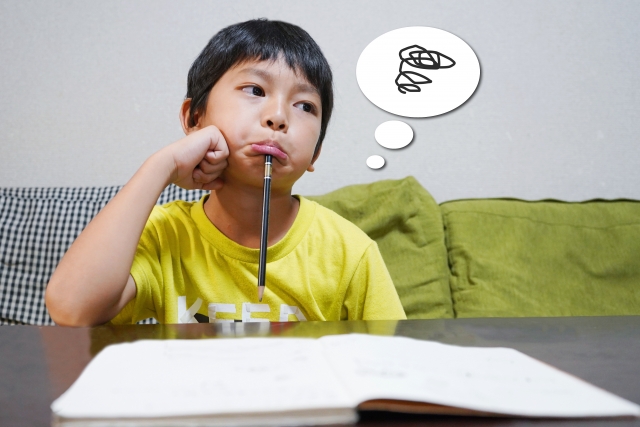
不登校のきっかけの第1位は「不安など情緒的混乱」で、第2位は「無気力」。
これは5年連続となっていて、「不登校は子ども本人の問題である」と結論づけされています。
しかし、注意してほしいことは、これは「実情を知らない学校側が調査をして発表した理由」だということです。
「実際に子どもに聞いた理由ではない」「子どもが理由として言ったのではない」ことを知るべきです。
子どもが不登校なったのは学校教育の制度不良によるもの
さらに、「不安など情緒的混乱」や「無気力」になったのは、「子ども本人の問題」ではなく、その要因は学校にもあるという見方をすべきです。
教職員の不適切な対応や子どものニーズに応え切れない学校環境、学校教育制度の不備によってもたらされたともいえるのです。
保護者の方と話をして出てくる理由の多くが、担任の初期対応のまずさです。
担任や校長の不適切な対応によって、子どもと学校との距離が遠くなっているケースがほとんどです。
学校がいかに子どものことが理解できていないか、受け入れる体制が十分整っていないかが分かります。
まずは、子どもの声をしっかりと聴くこと。しっかり聴くことのできる「人」になることから始める必要があるのです。
子どもとの関係も親同士の人間関係も再構築すべき
先生との人間関係や初期対応のしかたによっても違ってくると思いますね。
そして、不登校というと「先生の理解が・・・」ということがクローズアプされますが、親の理解も必要です。
ただ、子どもにとっては「自分の親だからこそ言いにくい」ということもありますので、信頼できる人の存在が求められますね。
教員の管理が強化され、先生方も身動きがとれない、上から言われたことだけでもこなすのが精一杯だという現実があります。
しかし、自助努力によって忙しさを減らすことは可能です。
教員一人ひとりが声を上げ実行することによって時間を作ることも可能です。
ただ、これも教員一人ではできることではありませんので、みんなが連帯して変えていく必要があります。
これは、教委や文科省にもいえることです。
その時間を子どもや保護者との関わり合いの時間として使っていくことでコミュニケーションもできます。
地域の教育力についても随分前から言われていますが、子どもがどうこうという前に大人同士の関係作りを見直していく必要がありますね。
鳥取ではこの度の地震で地域のつながりの大切さを痛感しました。
先生が理由で不登校する子は2%しかいないってホント?!【緊急アンケート企画】(不登校新聞)
「不登校の理由は先生との関係」子どもと学校との回答に16倍の開きがあった!
学校に馴染むことができない理由
日本財団は、少子化が進む中で増加する不登校の子どもの実態を把握すべく、文部科学省が定義する不登校児童生徒に加え、学校に馴染んでいないと思われる子どもたちの実態について調査を実施しました。
調査は、2018年10月に中学生年齢の12歳~15歳合計6,500人を対象にインターネットで行いました。その結果、「年間30日以上欠席の不登校である中学生」は約10万人、「不登校傾向にあると思われる中学生」は10.2%の約33万人に上ることがわかりました。不登校である中学生約10万人は文部科学省が各学校、教育委員会からの回答を基に集計して、毎年実施している調査でも明らかとなっていますが、「不登校傾向にあると思われる中学生」の数はその3倍にも上ることが初めて明らかになりました。
今後の不登校対策に大きな意味を持つ数字と思われます。このほか、学校に馴染むことができない理由として、「授業がよくわからない」、「授業内容以外に追求したいことがある」などの意見が目立ちました。
不登校傾向にある子どもの実態調査(日本財団)










