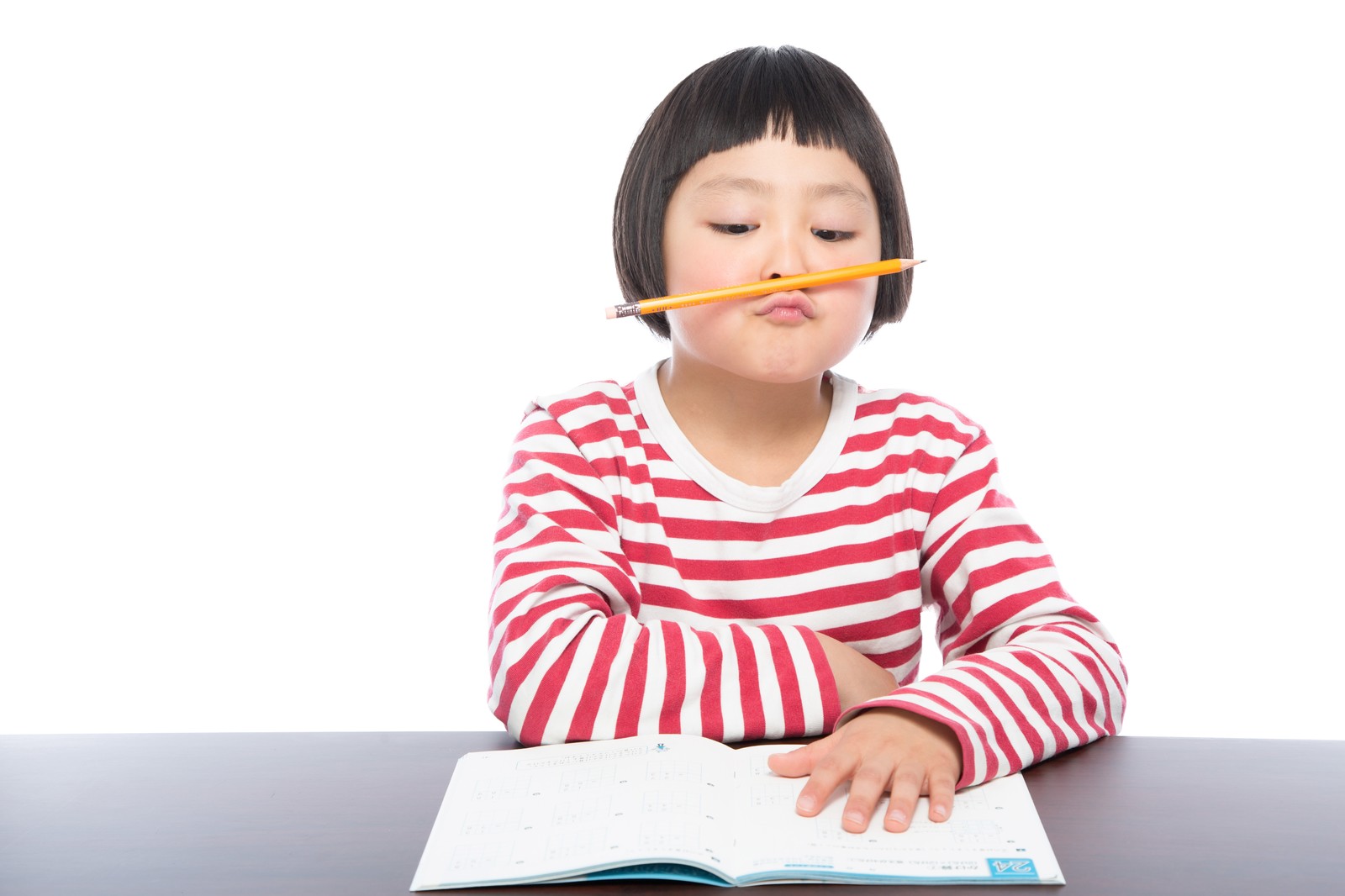
世間から「学校を休んだり、逃げたり、撤退するということへの否定的なまなざし」が強いのは確かです。
学校に行く行かないの自由は認められたとしても、現在不登校をしている子どもたちが「学校に行かなくても、何かをしていなければならない」というプレッシャーを感じることなく過ごせる環境を作っていくことが必要です。
「こうならなくちゃいけない」「こうあらねばならない」という考え方は、ますます自分を追い込んでしまいます。
別に「こうならなくちゃいけない」ことなんかないんです。
決められないままだっていいんです。
何かを前向きにやっている人も、(周囲から)何もしていないと”見られている”人も、ありのままでいること自体に価値があります。
存在そのものに価値があります。
不登校の子どもたちやひきこもりの人だけでなく、社会的な評価の目が厳しく感じられるために、自己の価値に気づけない人が多いです。
「自分がそうしたいからやっている」
「あなたの存在そのものが誰かのためになっている」
「あなたはあなたであるから素晴らしいんだ」
不登校対策やひここもり支援にしても、この点が欠けていると思っています。
根本的な「してあげる」とか「やってもらっている」という受け止め方を変えていく必要があります。
何が価値があるかなんて、絶対的なものではありません。
その価値を決定できるのは、他者ではなく自分自身です。
「不登校を選択肢のひとつとして、学校外で学ぶことを認めてほしい」というと、こんどは休むことも許されず、不登校でも学んでいないと認められないことになってしまいがちだ。そうなると、休んだり、逃げたり、撤退するということへの否定的なまなざしは変わらなくなってしまう。
学校に行かなくても、何かをしていなければならない。というプレッシャーを、現在不登校をしている子たちが感じることなく、過ごせているといいんだけど……と、最近の不登校に関する新聞記事を読むたびに、祈るような思いでいます。
私も不登校をした当時、学校に行かなくても、何か自分の将来につながるようなことをしなければ、というプレッシャーを、すごく感じていました。家に東京シューレの子どもたちの不登校体験を集めた本『学校に行かない僕から学校に行かない君へ』と『僕らしく君らしく自分色』(もう手元にないのですが、こんな題名だったと思います)があり、それを読んで、「不登校をしても、こんなに元気な私たち!」みたいなメッセージを本の内容からビシビシ感じてしまい、〈私もこうならなくちゃいけないんだ〉と思ったのを覚えています(本を作った人たちの意図は別にあったかもしれませんが、私はそんなふうに受けとめてしまいました)。
学校に行かないなら別の場所へ行ってほしい、学校へ行かなくても規則正しい生活をして、何かを学ぶ姿勢をみせてほしい、という周囲の視線に、当事者はものすごく敏感です。
学校に行かなくても、何かをしていなければならない。というプレッシャーを、現在不登校をしている子たちが感じることなく、過ごせているといいんだけど……と、最近の不登校に関する新聞記事を読むたびに、祈るような思いでいます。朝日新聞の1月31日朝刊で不登校が大きく特集されましたが、「未然防止」「早期発見」など、病気に対して使われるような言葉が並んでいたため、「人をなんだと思っているのでしょうか。この言葉を読んだ当人がどんな気持ちになるか、全く考えていない発言です」という趣旨の抗議のメールを、新聞社宛てに送信しました。
やはり「義務教育の段階に相当する普通教育の機会の確保に関する法律案」が国会に上程されるかもしれないために、「不登校」の周辺が、にわかに慌ただしくなっているのでしょうか。
数日前、不登校新聞の『「多様な教育機会確保法案」は危ない 桜井智恵子さんに聴く』を読み、桜井さんの「どんな制度になっても、どんなに社会の状況が悪化しても、要は人ですから、そこを信じてやっていくほかない」という言葉を、ひとつの希望のように感じました。
今回の法案に関しては、本当にあちこちからいろいろな意見が出ていますが、法案をめぐってどう思うかに心身が傾きすぎると、自分を含めたひとりひとりの心の動きや感情が、見えにくくなります。
法案が成立しても、廃案になっても、ひとりひとりの時間は続いてゆくので、そのことを忘れないようにしたいと思いました。
(小学校でいじめにあい、中学2年で学校に行かなくなった30歳の不登校経験者より)
引用元:「迷子のままに」山下耕平(やました・こうへい)










