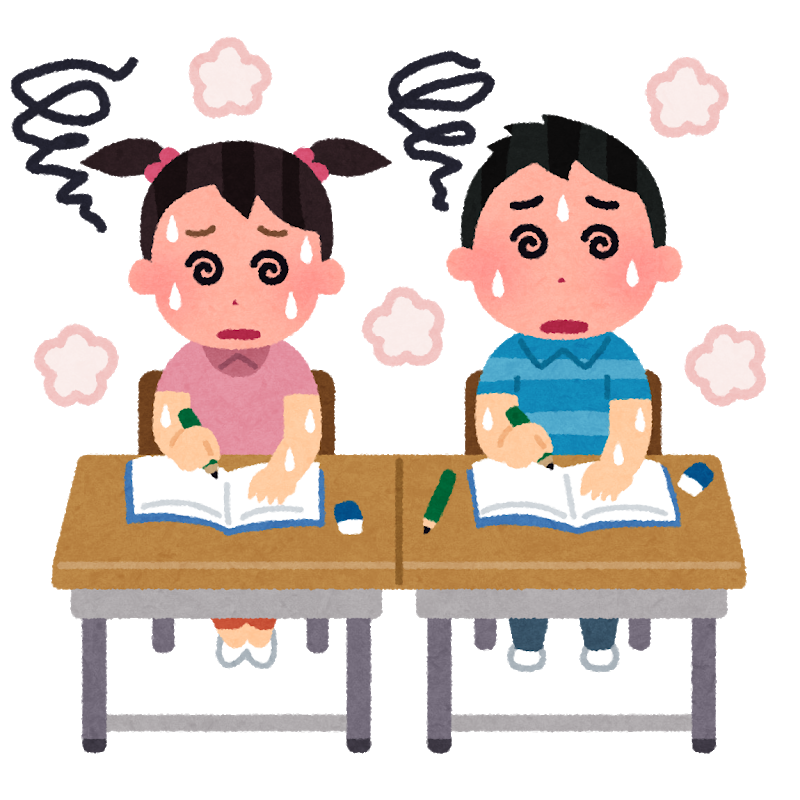
子どもたちが学校が楽しくない、行きたくないとというのはごくごく当たり前です。
園の保育士や学校の教員という「教育の専門家」と呼ばれる人たちが子どもから自信を奪っている。
まずはそれに気づいている者が何人いるだろうか?
「子どもの気持ちに寄り添い、一緒に悩みや困りごとを考えてくれる先生が増えれば、子どもたちはきっと笑顔と自信をとり戻していくでしょう。」
寄り添うことはできる、一緒に考えることもできる。
しかし、現実を変えられる学校関係者はいない。
子どもは一人ひとりちがうのにみんな同じにしようとする。
そんな学校システムの中にはめようとすることははじめっから不可能です。
にも関わらず園や学校ではみんな同じにさせようとする。同じことを目指して、それだけで子どもを評価し序列化する。
子どもたちが学校を「嫌いにならない」「嫌いにさせない」ために何をしているのか?
学校のシステムを変えようとしている学校関係者は何人いるのか?
システム、その中身を変えない限り学校は何百年も変わらない。
だから、学校に行きたくない子どもはこれからも増え続けて行く。
その反対に自分で課題を見つけて自由に学び始める子どもが増えて行く。
「学校にNo!」という子どもが増えるのは決して悪いことではない。
これからもそんな子がどんどん増えたらいい。
そうしたら当たり前が当たり前になる社会に近づいていくと思う。
園の保育士や学校の教員という「教育の専門家」と呼ばれる人たちが子どもから自信を奪っている。
まずはそれに気づいている者が何人いるだろうか?
子どもは一人ひとりちがうのにみんな同じにしようとする。
そんな学校システムの中にはめようとすることははじめっから不可能です。
にも関わらず園や学校ではみんな同じにさせようとする。同じことを目指して、それだけで子どもを評価し序列化する。
そんなところには別に行かなければいいだけのことだよ。
子どもの気持ちに寄り添い、一緒に悩みや困りごとを考えてくれる先生が増えれば
気になる子は、困っている子
これは鳥居深雪先生の著書に出てくる言葉です。「夏休み明けから学校に行きたくない!」という日が増えて心配です。
先日、小学校1年生の相談を受けました。
お話を伺うと保育園の時は、行きたくないということがなかったけれど、春から小学校に入り、6月、7月と月が経つごとに「学校に行きたくない」「お腹が痛い」という日が増えてきたようです。
7月末からは夏休みに入ることもあり、お母さんは「2学期になればきっと行けるようになる。」「なってくれる。」と思っていましたが、2学期に入り最初の3日間は行くことができましたが、4日目になると「やっぱり行きたくない」と訴えたそうです。初対面で本人も緊張していましたが、気持ちをほぐしながら聞いてみると「保育園は楽しかったけど、小学校は楽しくない」
「学校に行っても座っているだけやし!」
お母さんは「読み書きが苦手なところがあるかも知れない?」
と伺っていたので本人に了解をもらって読み書きと視機能のスクリーニング検査を行ってみました。ひらかなの1語を読むことや書くことには全く問題がありませんが、単語の書きと図形の視写、音読などに少し苦手さがあることが分かりました。
これまで保育園や小学校では「気になる」と言われたことはなかったそうですが、お母さんは「気になって」いたそうです。
保育園や小学校の先生は、保育、教育の専門家としてこれまでたくさんの子どもたちを見てこられています。「おや?」と少し気になることがあったら、
「頑張ったらできるようになります」
「まだこの年齢ですから、差があるのは当然です」
「お母さんが心配し過ぎでは?」
と終わらずに、
「この子は何か困っていることはないかな?」
「活動に参加できないのはなぜかな?」
「お母さんが心配していることは何故かな?」
学校に行きたくない。勉強が楽しくない。
のはその子その子に理由があるからではないでしょうか?
学校や勉強との関わりが始まったばかりの子どもたちが
「嫌いにならない」「嫌いにさせない」
気になる子は、困っている子
子どもの気持ちに寄り添い、一緒に悩みや困りごとを考えてくれる先生が増えれば、子どもたちはきっと笑顔と自信をとり戻していくでしょう。










