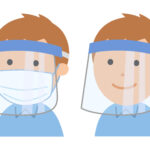学校教育の基本が「指導」であることが勉強をつまらなくしています。
「学び合い」の形でなければなりません。
私も違和感を感じている一人です。
上辺だけカッコつけている人間は大嫌いです。
「子どものため」といっていながら、自分の立場を守るため、責任回避のために保身優先で逃げていては教育者失格です。
多様性を認め合う世の中を作るためには、まずは「正しく知る」ことから。
知る→理解する→自分の意識を変える→関わる→周りを変えることにつながっていきます。
周囲の先入観や間違った認識が「障害」を「障害」にしています。
他人を変えることは難しいですが、自分の意識や行動を変えることはできます。
そのために最も大切なことが「教育」です。
すべての人に知ってもらい、できることをしていきたいです。
なぜ自閉症は急激に「増加」したのか 忘れられかけていたアスペルガー氏の論文と、いくつかの偶然の物語
http://logmi.jp/82832
ようやく1980年代後半から広まった自閉症への理解
投稿日:
執筆者:azbooks