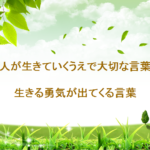「発達障害特別措置」の申請について、「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」の有無についても書くことといいましたが、2016年5月25日、発達障害者支援法の改正案が参院本会議において全会一致で可決、成立しました。
この支援法は、2005年に施行されたもので、改正は約10年ぶりです。
改正支援法の内容は、1人ひとりの特性に合わせ、学校では個別の計画を作成したり、雇用の確保を求めるなど、今回の改正は「教育・就労の支援」が柱となっています。
発達障害がある子供が他の子供と一緒に教育を受けられるように配慮。
学校側が目標や取り組みを定めた個別の計画を作成し、いじめ防止対策や、福祉機関との連携も進める
国や都道府県が働く機会の確保に加え、職場への定着を支援するよう規定。
事業主に対し、働く人の能力を適切に評価し、特性に応じた雇用管理をするよう求めた。
改正発達障害者支援法が成立 学校で個別計画、雇用確保
発達障害者が「切れ目ない支援」を受けられるよう、国と自治体に教育現場でのきめ細かい対応や職場定着の配慮などを求めています。
この法案には、発達障害当事者や発達障害児を育てる保護者にとって、この法改正は画期的で大切なことが含まれています。
今回の「発達障害者支援法」改正のうち、重要なポイント
1. 発達障害者の支援は「社会的障壁」を除去するために行う
2. 乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援。教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携
3. 司法手続きで意思疎通の手段を確保
4. 国及び都道府県は就労の定着を支援
5. 教育現場において個別支援企画、指導計画の作成を推進
と、「発達障害を支援するのは社会の責任」であることが明記されました。
つまり、これらのことが法的な背景のもとに実施することが決まりました。
また、今年4月に施行された「障害者差別解消法 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、「合理的配慮」を可能な限り提供することが、行政・学校に義務付けられました。
公立の学校であれば、本人や保護者からの障害特性を理由とする要求に対して配慮しなくてはならない義務になりました。
発達障害の子どもへの「合理的配慮」の一つとして支援計画を作成して学校での生活や学習場面での具体的な対応をしていくことになっています。
障害のある子どもたちへの合理的配慮は特別扱いではなく、他の子どもたちと同じように学ぶ権利を保障するためのものです。
「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」について、「小学校学習指導要領」にも
障害のある児童などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。特に,特別支援学級又は通級による指導については,教師間の連携に努め,効果的な指導を行うこと。
と明記されています。
幼稚園教育要領、中学校、高等学校学習指導要領でも同旨の記述があります。
「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」について
法律や規則、社会の制度を知ることは生きるために必要なことです。
それらを知らないことは、それだけで「損」をしていることになります。だから勉強する必要があるのです。
勉強は、自分たちの命とくらし、人間としての尊厳を守るためにしています。
その社会のルールに乗っ取って「自分らしく生きる」ために自己の権利を主張したり要求を伝えることは特別なことではありません。
人が人として生きていくために当たり前なことです。
以下、発達障害者支援法の改正案のついての解説と文科省の通知を載せておきます。
「発達障害支援法」改正、押さえておきたい7つのポイントまとめ
学校での個別計画や、雇用先の確保。「社会的障壁」をとり除くために
改正発達障害者支援法が成立 就労定着の強化へ
発達障害者切れ目ない支援を…改正法案25日成立へ
特別支援教育の推進について(通知)文科省