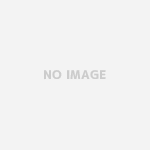本当に必要な「支援」や「配慮」ってなんだろう?
その先生が担任になってから息子の態度はガラリと変わりました。
「僕は出来ない子だ」と癇癪ばかり起こしていた息子が、行事のたびに「こんなことができるようになった」「こんなことが楽しかった」と話してくれるようになりました。
「支援」のフリ「配慮」のフリで教員の自己満足。
してもらう「支援」、してあげる「配慮」ではなく、それが当たり前にならなければいけません。
発達障害者支援法、障害者基本法、障害者差別解消法など法律はできただけで中身が伴なっていません。
謳い文句だけあっても、理解不十分で肝心な行動が行われなければ何の意味もありません。
先生たちの善意の「配慮」が、発達障害の息子を苦しめていたと知ったとき
子どもへの「支援」のフリ「配慮」のフリで教員の自己満足で終わっていませんか?
投稿日:
執筆者:azbooks