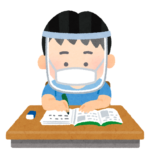保護者の中には中学校卒業後の進路を心配されている方が多いです。
中学校までは特別支援学級があるのに、高校は特別支援学級が設置されていませんが、発達障害などの障害があっても、もちろん高校進学はできます。
高校入学後も中学校から支援計画なども引継ぎが行われますが、形だけの引継ぎになっていることが多いので、個別に学校長や特別支援教育コーディネーターとしっかり話し合いをしていくことが重要です。
通級については2018年度から開始されるよう文部科学省が準備を進めています。
「通級指導」、高校でも 18年度開始へ文科省が準備(日本経済新聞)
「高等学校における通級による指導の制度化及び充実方策について」(文部科学省)
個別の支援計画は形だけの引き継ぎ?
「形だけの引き継ぎ」だと感じておられる方も少なくないと思います。
行政や学校は保護者からの要求がないとなかなか動かない場合があります。
これも学校にとって差がありますので、中身のある有効に活用される支援計画にしていくためには保護者の方がしっかりと子どもさんの様子や要望を伝えて支援会議を行うこと、そして継続的に支援の経過を確認していく必要があります。
支援計画は作ってからがスタートで、それを学校任せにしないできちんと実行できているかチェックすることも重要です。
保護者の方も学校への遠慮があったり気をつかったりすることもあると思いますが、対話を続けていくことによって学校の対応も変わっていきます。
そのためにも要望があればそれを伝えていくこと、保護者と学校でそれらを共有し共通実践していくことが大切です。
また、保護者の方と話をしていると、学校への対応の仕方についてよく分からないという方もあります。
そして、保護者の方から見たら残念なことですが、校長や担任によって理解度や対応の仕方が変わります。
支援学級の状況も学校によって差があるのも現実ですし、親身に対応してもらえた教員も異動がありますので、その点を不安に思われている方もあります。
中学校での高校への進路指導の課題
高校への進路指導についても、中学校単位である程度の形は準備してありますが、県内すべての高校を網羅できていませんし統一したものがあるわけではありません。
今では県内にもさまざまな高校がありますが、中学校によって高校説明会に来る学校も異なります。
実は私も県で統一したものがあるのだと思っていましたが、そうではないことを最近知りました。
中学校によって進学先の選択肢や情報提供の仕方が異なったりするのは改善していくべきなのですが、今の状況では保護者が自分でいろいろな高校を探して問い合わせるしかないのが現実ですね。
進路の決定権は本人にあるのですが、より多くの選択肢を準備しておくのが学校の役目だと思います。
あと問題になっているのが、障害のある子への高校入試の受験方法の配慮です。
高校によっては個別の配慮をしているところもあるようですが、「個人情報に関わる」とか「前例がない」ということで実現できていません。
県教委の特別支援教育課主催の「子どもを語る会」などでも、どうしてそのような体制が作れないのか、保護者の要望として出してはいるのですが、なかなか進んでいません。
高校での特別支援教育についてはようやく今年度から形が始まったところですから、保護者の方を中心に要求を強めていく必要があると思っています。
子どもの可能性やチャンスを広げるために情報収集を
行政は行政で、学校は学校で発信もしているのですが、なかなか行き届いていないです。
情報を知らないために子どもの可能性やチャンスを小さくしていることもありますので、自分の子どものために保護者が情報収集をしていく必要があります。本来は学校の役目なのですが。。。
それも親が一人でやるのは大変なので、親の会などで情報交換すると具体的な支援体制なども知ることができます。
高校受験については中学校の先生を通じて、入学後の相談については受験前から高校の先生と話をするのもありです。
体験入学やオープンキャンパスの時に個別支援について聞くこともできますし、基本的に学校はいつでも相談を受け付けているので、不安がある場合は早めに相談するのがいいです。
子どもさんの状態は個人情報になるので保護者の承諾も必要になります。
受験に当たっても一番の窓口は学校なので、担任を通じて要望を伝えて情報を集めておくのがいいです。
情報を集めて知識を増やしていくことも重要なことですから、これからも情報を発信していこうと思っています。
これらの情報もみなさんで共有していけたらと思います。
特別支援学級を徹底解説!障害ごとの教育内容から卒業後の進路まで