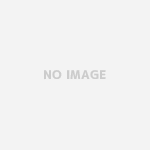幡野さんとまったく同意見です。
「これ買って」と子どもに言われたら、買った方がいい。
「これやりたい」と言われたら、なんでもやらせた方がいい。
「やりたくない」と言われたら、無理してやらせなくてもいい。
自分は自分の人生を生きたらいい。
親も学校も「子どものやりたいこと」ではなく、「大人がやらせたいこと」ばかり求めているような気がします。
親にできることは我慢させることではなく、子どもの選択権を奪わないことです。
子どもの夢を否定しないことです。それが子どもを信じるということです。
そうすれば、子どもの主体性がどんどん伸びていきます。
そうしたら、子どもの「これやりたい!」「これ勉強したい!」がどんどん増えていきます。
だから、家でも学校でも子どものやりたいから始めたらいいです
とにかく、どんなときでも、子どもに選ばせるというのが大切なんですよ。親は経験豊富ですから「このお菓子を食べたら子どもが体調を崩すだろう」とか分かってしまう。でも、子どもは失敗してみなければ、正しい選択をする練習ができない。失敗を恐れて挑戦しなくなって、自分の本当にやりたいことが何なのかすら分からなくなってしまう。
34歳でガンになった写真家・幡野広志さん。
「毎日悩み相談を受けた結果分かった。子どもの意見を尊重することが一番大事」
子が欲しがる物を買わないことが子の可能性を摘む