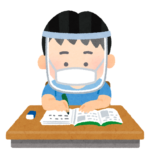4年前に教員の負担を軽減するためにも教育のICT化を進めることが必要だと言っていましたが、あれから4年経った今、教員のデジタル機器の活用についての意識が変わっているでしょうか。
相変わらず、スマホやタブレットは持ち込み禁止の学校が多いです。
その便利さを理解するどころか、子どもにとってスマホは危険、スマホは勉強の妨げになると考えている教員もまだまだ多いです。「授業中は先生に預けなければならない」「休み時間は使用できる」など、条件付きで許可する学校も少なくない。
勉強でのスマホ利用については、学校外も含めると、9割以上の中高生が「勉強でスマホを使用している」と回答しています。
中高生の9割、スマホ使って勉強「YouTubeで問題の解き方見る」(2017年12月18日)
学校や行政はオンライン授業でもたもたしているけど、子どもたちはとっくにオンラインでつながっています。オンラインでおしゃべりしながらゲームをしたり、動画を共有したり、音楽を作ったりしてお互いに「同時双方向型」の交流をしています。教員同士はオンラインでのつながりはまだまだできていないようで、慌てて連絡手段を考え始めている学校もあるようです。
子どもたちはとっくにオンラインでつながっている
この度の休校によって、いろいろなことが浮き彫りになっています。
中でも学校と保護者、教職員間の連絡体制。
オンライン授業どころか、学校の教員と保護者がオンライン通信できないのはもちろん、教職員間でさえ、いまだにFAXや電話しか連絡方法がない学校も少なくないようです。
さらに、学校からつなごうと思っても制限が多く、つながらない、資料のDLにも時間がかかるというネット環境らしいです。
Skypeって何?
Zoomって何?
Kindleって何?
Youtubeって何?
SNSって何?
Facebookやツイッターを日常的に使っている教員は何人いるでしょう?
言葉を聞いたことはあるけれど、よく分からない。よくわからないから使えない、危ない。
「それって、よく分からない、危険なんじゃないの」止まりの教員も少なくないのではないでしょうか。
ネットやデジタル機器について一番知らないのが、教員なのかもしれません。
今の時代に一番追いついていけていないのが教員なのかもしれません。
オンライン学習、教育改革、9月入学論議、学校の仕組みを変える前に必要なことは、教員の認識、意識を変えることの方が難しいのかもしれません。
まさかのキンドル禁止令?
新型ウイルスで「教育が止まりかねない」日本。止めない中国。浮上した「オンライン教育格差」
新型コロナ対応で懸念される「オンライン教育後進国」日本!
小中高一斉休校、オンライン授業開始に全力を!
ICT機器の整備よりも教員の認識、意識を変えることの方が難しいのかも
投稿日:
執筆者:azbooks