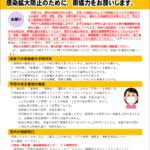長男が中2の時、友だちの一人が酷いいじめを受けて精神的に追い込まれていました。
親御さんは知人を通じて学校にも相談に行っていましたが、解決の方向へは程遠い対応でした。
保護者説明会も開かれましたが、「加害者のプライバシーに関わる」という理由で事実説明はありませんでした。
そのときに親御さんから個人的に相談を受け、有志の親たちが集まり「親の会」を組織し学校との交渉なども行いました。
しかし、その後も学校側から真実が明らかにされることはありませんでした。
「親の会」では苦しんでいる生徒や親御さんの相談に乗ったり、日ごろの子どもたちの生活の様子を情報交換したりして励まし合っていました。
学校とも何回か対話の場を持ちましたが、最終的には真実は分からないままとなっています。
この件は、いまだに私の中では納得のいかない事案として残っているままです。
それでも、「親の会」をはじめ、周囲の生徒や親の支えもあり、皆が卒業しそれぞれの進路に進むことができました。
今、子どもたちに関する様々な事件、事故が起こっていますが、文科省、教委、学校の教職員の隠ぺい体質は変わってはいません。
仙台のいじめ自殺についても、市教委はこれまで「遺族の意向」を理由に自殺に関して在校生や保護者にも何の説明もせずに来ています。
このような教委、学校の対応のまずさがますます保護者の不信感を招いて、さらに事を大きくしていることがなぜ分からないのでしょうか?
事実を出すことが学校現場にとってそんなに都合の悪いことなのでしょうか?
その背景には文科省、教委からの「学校評価」があります。
都合の悪いことを上に報告することは、学校、校長に不利になることがあるからです。
そんな考え方で学校教育を進めている限り、保護者からの信頼は永遠に取り戻すことはできません。
親も学校も、みなが安心して子どもを学校に通わせる環境作りを進めていかない限り、学校環境が原因となった子どもの自殺、事件もなくなることはありません。
一人ひとりが他人事だと見ないで、今できることを勇気と覚悟をもってやっていく必要があるのです。
文科省の命令自体がおかしなものになっていますので、文科省の体質改善と官僚の考え方も変える必要がありますね。
といっても期待はできないので、現場が団結して徹底して子どもの側に立つことが大事です。
現場から教委にはっきりとものを言える教員を育てていく必要があります。
また、保護者も日ごろから学校運営について関わりをもって、他人事として済まさない、ことが起こる前に絶対に隠ぺいを許さないという姿勢も必要です。
親の団結力が学校を動かし、教育委員会の意識も変えることができると思います。
私はそう考えて活動を続けていきます。
文科省、教委、学校の教職員の隠ぺい体質
投稿日:
執筆者:azbooks