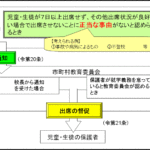あなたは「うるせえ、くそばばあ」と言われたらどんな言葉を返しますか?
それを翻訳すると、どんな言葉を返したらいいか分かりますよね。
「くそばばあ」って、「すごい母ちゃん!」「すごい母ちゃん先生」っていう意味なんだけどなあ。
待ってましたとばかりに、「そうか、そうか、そうだよねえ。くそばばあわかったよ。ありがと」ってな感じかなあ。
「くそばばあ」って言われたら、うちの子もちゃんと育ってると思ったらいいですね。
息子さんに感謝ですよ。
父親への場合は 「うるせえ~、くそじじい!」ですね。
翻訳するとしたら、親子の関係性にもよるし、人それぞれだと思いますが、「父ちゃん、俺は俺で頑張ってるからな」「オレ、言われなくてもちゃんとやってるからダイジョブだよ。」でしょうか。
父親に言葉をかけてくれるなんて、すごい子じゃないですか。
よくぞ「くそじじい」といってくれましたですね。
反抗期とは大人が勝手に作った言葉子どもは反抗しているのではない
そもそも「反抗期」という言葉が親や大人中心の表現なんですよ。
親や大人に従わない、いうことを聞かないから「反抗」なのですか?
これって、親や大人が子どもを支配しようとしていることから出てくる発想なんですよ。
子どもからしたら、ごく当たり前の「反応」をしているだけなんですよ。
しかも、「くそばああ」が出てくる背景や理由もちゃんとある。
その理由を作っているのは、親や大人の側です。これじゃあ、子どもの側からしたらたまったもんではないでしょ。
そして、「るせえ、くそばああ」と言って、親とちゃんと向かい合ってるわけです。
本当に顔も見たくないほど嫌なら、そんな言葉を返さないで無視しますよ。
「くそばああ!」は喜ばしいこと
私が親の会などで話しているのは、子どもがちゃんと成長していると受け止めて、「そうか、そうか、言ってくれてありがとう。」って返したらいいですということです。
子どもにとっては「反抗期」ではなく「成長期」の一段階なんです。自分で考え判断し、決める力がついてきているのですから、怒るどころか喜ばしいことなんです。
それをいうのはいつもいつもではなくて、親が何かしたり言ったりしたときの台詞なんです。何もしていないのに急に言ってくるように見えても、言う理由や背景がちゃんとあります。
「何も変なこと、気に障るようなことをいっていないのにどうして?」というのも親の勝手な言い分です。
親は日常会話をしているようでも、それが子どもに対する一方的な命令であれば、素直に受け入れないのは当たり前です。
特に、「あなたのことを思って言っているのよ。」という言葉ほどカチーンとくる言葉はありません。
「何があなたのためだよ。それはあんたのためだろ!」となってしまいます。
それを親の勝手な都合で子どもをコントロールしようとするから、「くそばああ」と言われると頭にくる。頭にくるのも親の勝手でしょ。
思春期の「うるせえ、くそばばあ」を翻訳すると、こうなります
こんなことを言うと、翻訳しても「うっせえ、くそばばあ!死ね!」としか反応できなくなります。
子どものやる気をますます奪っていきます。
言えば言うほど逆効果!子どもがやる気をなくすNGワード8選