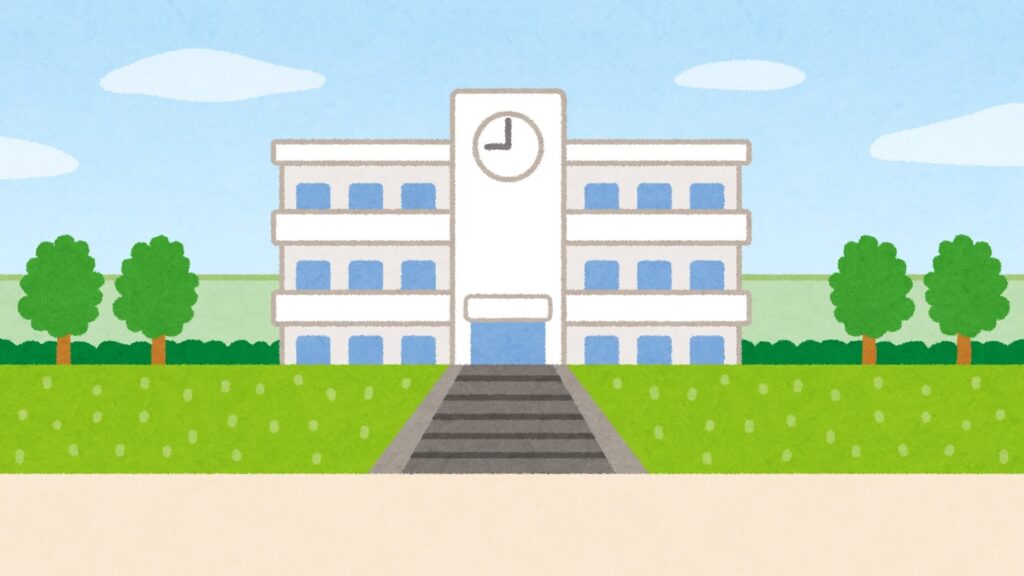
アットマーク国際高校・明蓬館高校理事長の日野公三さんが「ディスレクシアを持つ生徒の中学選びのための14のチェックポイントver.1.0」を公開しておられます。
発達障害のなかでもディスレクシアの生徒の場合、中学校を選ぶチェックリストとして押さえておきたいのは、以下の点です。
これらの点を念頭に置いて中学校を眺めるととても重要な何かが見えてくるでしょう。
1)学校の教職員が発達障害の正しい診断名と診断基準、特性について答えられるか
2)教職員がネガティブな言葉、態度を意図せずに安易に用いず、ポジティブな言葉、態度を意図して自然に用いているか
3)学校内に心理発達(アセスメント)を重視する(少なくとも軽視しない)体制があるか、医療機関との緊密な連携体制があるか
4)生徒数に見合った、臨床心理士や特別支援教育の学習支援者、精神保健福祉の有資格者がいるか(常勤であることが望ましいが、非常勤であっても構わない)
5)特別支援教育コーディネーターが任命されているはずだが、実際に動いているか
6)これまでの成育歴、支援歴などの資料の提出を要望されるか、聞き取りをしてくれるか、その姿勢は有るか
7)眼科医、心療内科医、療育専門機関からの参考資料、所見、引継ぎを重視してくれるか、少なくとも軽視をせずに聞き取りをしてくれるか
8)個別教育支援計画(IEP)の運用は行われているか
9)校長あるいは副校長が議長を務め校内委員会、ケース会議は定期的に行われているか
10)保護者への相談支援は行われているか
11)障害をおぎなうべくデバイス(PC、タブレット、スマホなど)やデジタル教材(アプリなど)、その他補助ツールで学習に取り組めるよう配慮されるか
12)生徒がWebベースで学びやすい認証ページ(学習支援システム)および生徒管理システムは稼働して、教職員が使いこなせているか
13)登校時に落ち着いて学習に取り組めるブース環境は用意されているか
14)教室内、学校内で他の生徒・教員の理解と協力が得られるよう障害特性開示が適切に行われるか。本人の人格と学習権が守られる中、管理職のバックアップのもと、担任、学年主任、特別支援の職員によるチームにより計画的に行われるか
以上
© 2017 Meihokan SNEC(明蓬館高等学校SNEC)「明蓬館高等学校SNEC作成」
発達障害の子どもたちが通える学校は、理解、スキル、システムの3つが必要ですが、現実にはなかなかありません。
理解ある教員がいたら、しようという努力はしてくれますし、個人で熱心に指導に当たっている者もいます。
また、保護者が子どもの思いや願いを伝え、環境や対応のしかたについて要望していくことも必要です。
ディスレクシアを持つ生徒の中学選びのための14のチェックポイント
投稿日:
執筆者:azbooks










