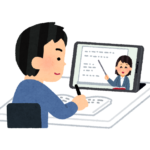昨日は、東伯文化センターで行われた不登校・発達障害の親の「虹の会」に参加しました。
この会は中部地区の中学生の保護者の集まりですが、初めて参加される方も増えています。
私自身も、この会に行くことがとても楽しみになっています。
子育てについてや進学についての悩みなど、母親として日ごろ考えていることをざっくばらんに話せるとても居心地のいい場となっています。
「虹の会」の大きなテーマは「みんなが笑顔になるために」です。
子どもが生き生きと自分らしく過ごすには、お母さんが明るく楽しく過ごすことが一番だと考えています。
そして、子どもを信じて見守り、本人の決定が出るまで待つこと。本人の決定を100%受け止め、できたことを一緒に喜び合うこと。(「ほめる」のではなく、「共に喜ぶ」ことがポイントです)
これが、親子関係でもっとも大切なことです。
学校に行くとか行かないとか、就労するとかしないとかは第一義ではありません。
親子で毎日が楽しいと感じられることによって、必ず子どもは自己決定ができるようになります。するときが必ずやってきます。
選択肢は人の数だけありますので、そのときに本人がどれを選ぶかを決めるだけです。
親はそれを信じて、いろいろな情報を得たり親の会などで交流をしていきながら子どもの決定を待つ、決めたことをできる限りサポートしていくことだけです。
その間、お母さんも自分の好きなことや楽しめることをやっていけばいいんです。
今では個人的にもいろいろな人たちとの関わりを持っていますが、最終的には子どもたちは皆、自分自身でゆく道を決めて歩んでいます。
その途中で新たな壁に当たることもありますが、そのときも同じ対応を繰り返すだけでOKです。
ただ一つだけ、絶対にやってはいけないことがあります。
それは「親が子どものゆく道を決めて、親の期待通りに進ませること」です。
親は自分勝手な期待と希望を持っていますが、それは子ども自身の願いではありませんから、そういわれたり、いわれなくても親がそう思っているだけで「うざく」感じとります。
これは、甘やかせることでもわがままを許すことでもありません。
子どもの主体性を育てるために必要なことなのです。
・・・と綴っていたらマイケル・フェルプスの話題を見つけました。
マイケルは9歳の頃、ADHDの診断を受けました。
体が細く、背が高くて、耳が大きかったので、学校ではいじめを受けたといいいます。
そして、一人の教師が母親にこう言ったといいます。
「あなたの息子はなにかに集中することができるようになることはないでしょう。」
しかし、マイケルの母親は、マイケルの育児についてこう語っています。
「私は命ずるため、指導するためにいるのではありません、私は彼のやりたいことに耳をかたむけ、問題を解決し、賢明な決断を下すように助けようとしてるだけです。」
その間、彼は水泳に打ち込み、10歳の時、自身と1つ上の年代のナショナルレコードを更新。11歳の時、コーチのボブ・ボーマンに出会います。
ADHDの診断を受けてから2年間、「リタリン」というADHDに対して処方される薬を服用していたのですが、マイケルが母親に薬の服用をやめたいとこういいます。
「もう、これ(リタリン)を飲みたくないよ。
ママ、友達は飲んでないよ。(飲まなくても)ぼくもできるよ。」
自分が泳いでる姿を何度も繰返しビデオで見て、繰り返し研究するという方法が、ADHDのマイケルに向いていたのかも知れないと言われています。
マイケルの学校の教員の一言は、決してまれな事例ではなく多くの子どもたちや親御さんが体験していることだと思います。
この教員の理解のなさと適切な対応方法が分からないだけでなく、心の中に差別意識が潜んでいると考えられます。これは決してこの教員だけでなく、残念ながら世間でもそう考えている人はたくさんいることも事実です。
マイケルのケースはお母さんの育児方針とボブ・ボーマンコーチとの出会い、彼にとっての学びかたがマッチしていたことによるものが大きく影響していると思います。
しかし、彼が決して特別な才能を持っていたわけではありません。
彼に合った周りの環境と適切な対応によって彼がここまで成長できたのではないでしょうか。
もしも、そのような環境や出会いがなければADHDによる二次障害(二次症状)を引き起こしていたかもしれません。
発達障害(ADHD)だった最強のスイマー、マイケル・フェルプスと、彼を見守った母親
発達障害の診断は気づきのスタートであり、その特性の理解と支援からアプローチしていくことで誰でもが自分の持っている力を発揮することができます。
私たちにできることは、そのような環境作りや人との出会いの場の設定なのだと思います。
これからもいろいろなところに出かけて「おせっかい」をしていこうと思っています。
「虹の会」の世話役の方、東伯文化センターの方、おいしいスイーツを毎回届けてくださるNさん、参加されたお母さん方、とても有意義な時間をありがとうございました。
鳥取県内には各地にこのような親の会があります。
8月20日には米子でも会がありますので、大歓迎です。
このようなつながりができることがうれしいです。
どこの親の会も温かい雰囲気で毎月の例会を開いています。
親の会には、教育講演会や研修会では得られないものがあります。
立場や肩書きではなく、すべての人がフラットな関係で結ばれている場は、ここしかありません。
どうぞお近くの親の会においでになってみてください。
倉吉トトロの会の案内はこちら
不登校の親の会「虹の会」のテーマは「みんなが笑顔になるために」
投稿日:
執筆者:azbooks